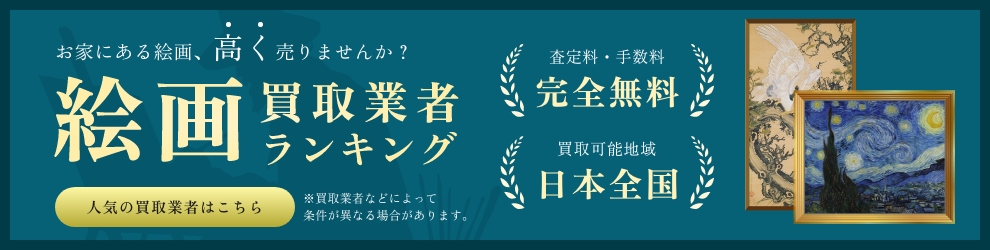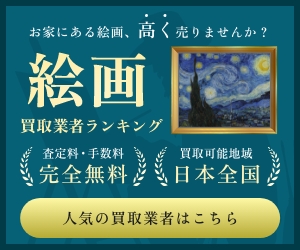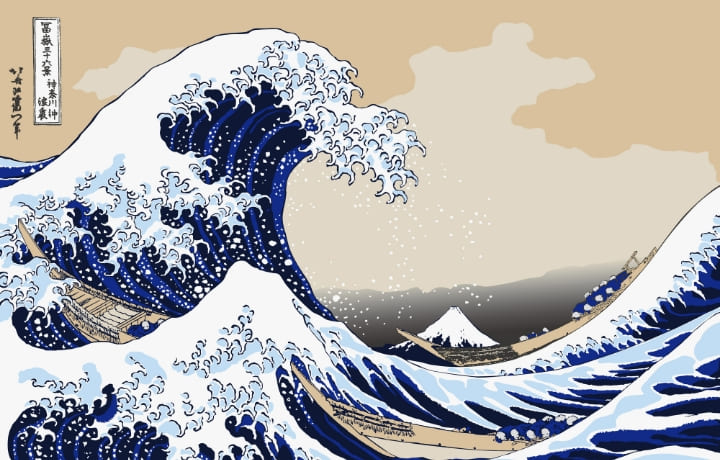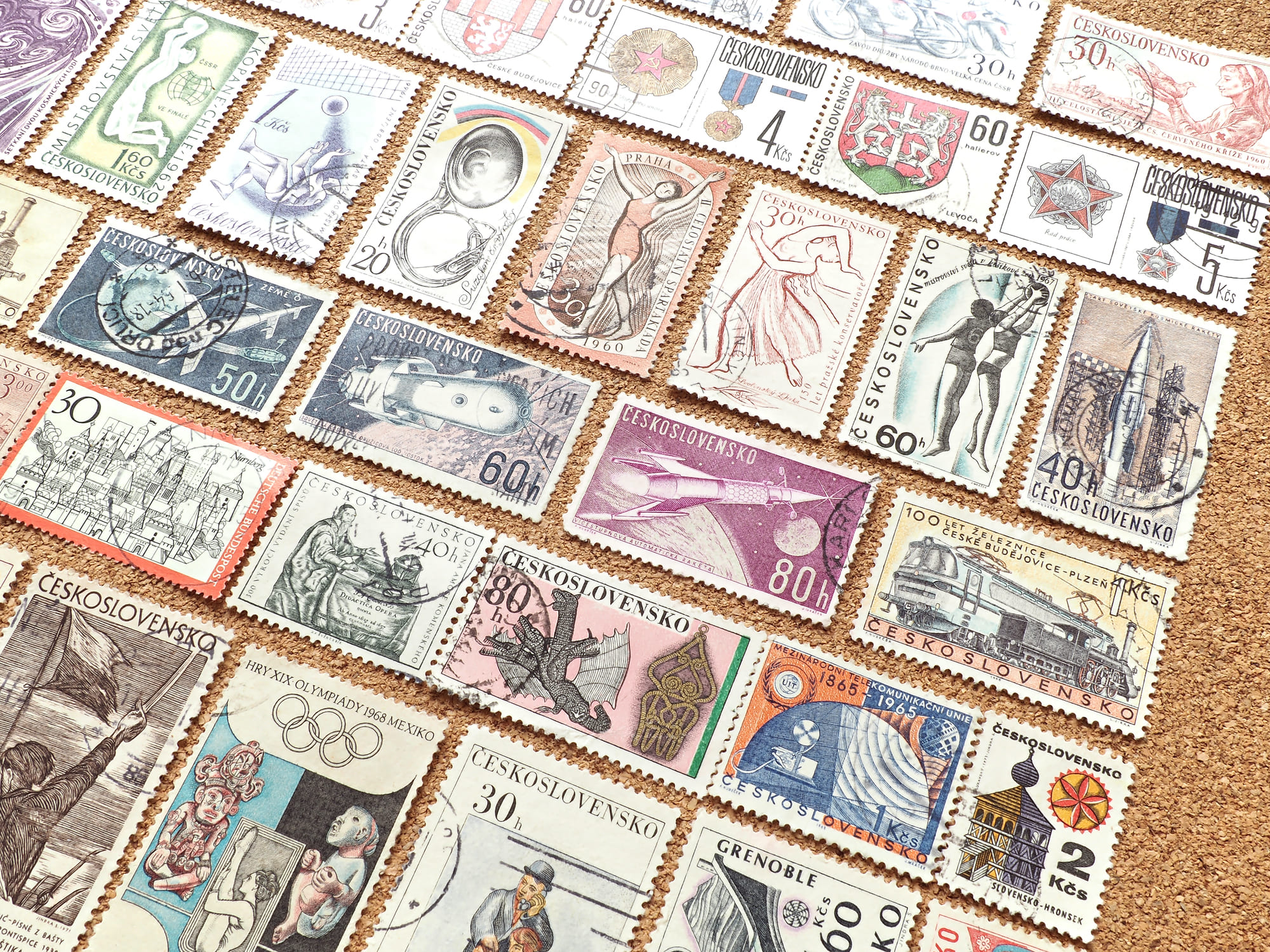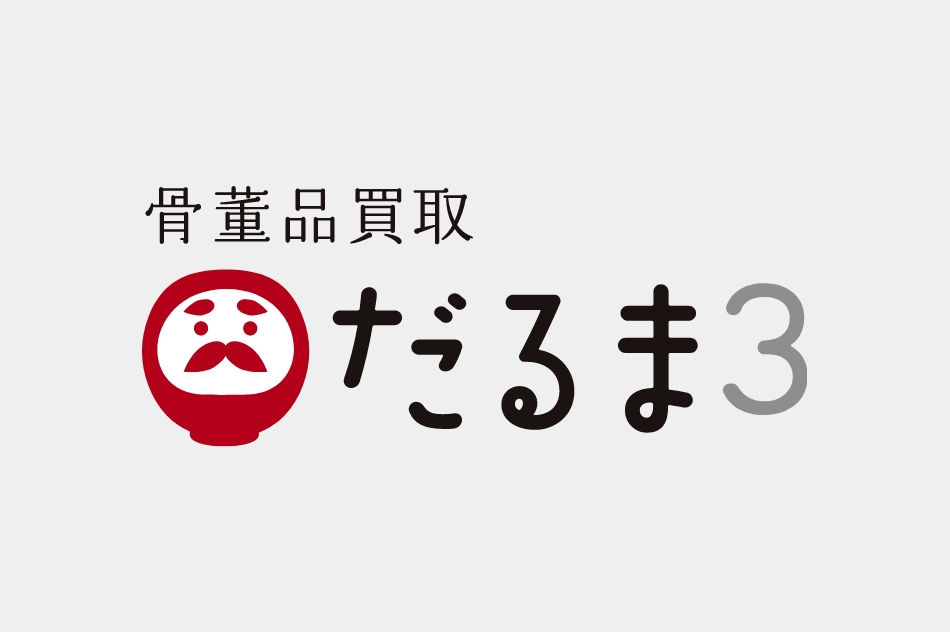仏画は、仏教をテーマにした絵や仏様を描いた絵を指します。
崇拝や礼拝のために用いられる場合もあれば、仏教を広めるために用いられることもある絵画です。
仏画はさまざまなジャンルに分類され、それぞれ表現している意味合いが異なります。
また描かれる仏様がとっているポーズにもそれぞれ異なる意味が込められているのです。
目次
仏画のジャンルは主に6つ
仏画は主に6つのジャンルに分類されます。
・崇拝・礼拝の対象
・曼荼羅
・変相図
・浄土図
・六道輪廻思想画
・垂迹画
崇拝・礼拝の対象
仏画は、仏様を崇拝・礼拝するためのものでもあります。
そのため、如来や菩薩などさまざまな仏様が描かれた仏画のジャンルがあります。
曼荼羅
曼荼羅とは、仏教の中でも特に密教の世界観を描いた仏画のことです。
仏教の教えや世界観を、鮮やかな色彩と幾何学模様で表現しています。
密教は、インドで生まれた仏教の一つで、修行によって仏と一体化できるという教えで、身・口・意の三密業を通して仏と一体化するとされているのです。
また、曼荼羅は悟りの仏である大日如来の世界観を表現しているともいわれています。
変相図
変相図とは、仏教における極楽浄土や地獄などを描いた仏画で、曼荼羅に雰囲気が似ているのが特徴です。
そのため、浄土曼荼羅と呼ばれることもありますが、密教とは関係していません。
浄土図
浄土図とは、平安時代後期によく描かれるようになった、仏教の末法思想の影響を受けた仏画です。
法然や親鸞が唱える浄土信仰が広まり、浄土図がよく描かれるようになりました。
六道輪廻思想画
六道輪廻思想画とは、仏教における世に生きるものはすべて六道と呼ばれる6つの世界を輪廻し、生死を繰り返しているという思想を描いた仏画です。
六道とは、生きていたころの行いによって決められる死後の6つの世界を指しています。
・天道界
・修羅道界
・人間道界
・餓鬼道界
・畜生道界
・地獄道界
輪廻とは、霊魂は不滅で何度も生まれ変わるという考え方を表しており、前世や過去の行為が原因となり、現在の結果がもたらされるという因果応報の世界が描かれているのが六道輪廻思想画です。
垂迹画
垂迹画とは、仏教と神道が融合した仏画で、垂迹とは神を指しており、仏教と神道の両立を目的として描かれました。
仏様や菩薩が垂迹と呼ばれる神に姿を変えて、困っている人々を救うために現世に現れるという本地垂迹説のエピソードに則って絵が描かれています。
曼荼羅のような雰囲気の仏画が多いのも特徴の一つです。
仏画に描かれる仏たち
仏画に描かれている仏様たちの種類は複数あります。
仏画に描かれている仏様の姿かたちが作品により異なっており、疑問に感じたことがある人もいるでしょう。
仏様は主に4種類に分けられ、それぞれ違う役割を担っているのです。
如来
如来とは、この上ない悟りを開いた者や真理に到達した者のことであり、仏教では最も位が高く尊崇される存在です。
如来には、三十二相と総称される身体的特徴があるといわれており、仏画に描かれる如来像は、この特徴を踏まえた姿で描かれています。
如来の特徴のうち強い印象があるのは、パンチパーマのような螺髪と呼ばれる髪型でしょう。
螺髪は三十二相のうち、体毛がすべて右巻きに巻くという特徴を表したもので、螺髪によってほかの仏像と区別がしやすくなっています。
なお、髻を高く結い上げる大日如来は、如来の中でも例外の仏様です。
他にも如来の特徴には、白い巻き毛の白毫や、如来像の首にある3本のシワである三道、印相の一つである施無畏印、本来修行僧が着る納衣、薬を入れた薬壺、如来が座っている蓮華座などがあります。
主な如来は以下の通りです。
・釈迦如来
・阿弥陀如来
・大日如来
・普賢菩薩
・薬師如来
・盧舎那仏
菩薩
菩薩とは、悟りを開いて如来になるために、生きとし生けるものを救済するべく菩薩行を続ける仏たちを指しており、如来の次に位の高い仏像です。
菩薩は、如来の意思に従ってさまざまな姿に変身し、人々を助けたといわれています。
菩薩は長い頭髪を高く結い上げ、上半身は裸、両肩に天衣をかけて条帛と呼ばれる布をたすきのようにかけているのが特徴です。
また、仏教を開いた釈迦が古代インドの王子であったことから、宝冠やアクセサリーなどを身につけた華麗な姿で表現されることも多くあります。
主な菩薩は以下の通りです。
・観音菩薩
・文殊菩薩
・弥勒菩薩
・普賢菩薩
・地蔵菩薩
明王
明王とは、忿怒の姿をした恐るべき仏様のことであり、如来や菩薩に次ぐ位であるといわれています。
明王は、仏教にヒンドゥー教を取り入れ発展していった宗教である密教から生まれた仏様です。
明王の姿は、人を諸悪から災害から守るとともに、煩悩により悪に走ってしまう者を威力で教化する姿であり、如来の化身や如来が忿怒した姿ともいわれています。
悪と戦う仏様のため、武器を持っていたり、髪を激しく逆立たせていたり、牙が生えていたりとおそろしい姿をしているのです。
主な明王は以下の通りです。
・不動明王
・愛染明王
・孔雀明王
・大威徳明王
・軍荼利明王
・降三世明王
・金剛夜叉明王
天部
天部とは、仏教や仏法を守る神さまのことです。
バラモン教やヒンドゥー教、各地域の民間信仰の神々などが仏法を守る護法善神として、仏教に取り入れられました。
仏教の信仰を妨害する者から如来や菩薩、人々を守る役目を担っており、天部は自然現象や抽象的なもの、半身半獣などの姿で表されることが多くあります。
主な天部は以下の通りです。
・梵天
・帝釈天
・毘沙門天
・吉祥天
・弁財天
・広目天
・多聞天
・増長天
・持国天
その他
仏像には、仏様以外の人物を表現したものもあり、仏様と同様に徳が高く守護神としての役割を担っているものも多くあります。
たとえば、羅漢は悟りを開いた高僧の阿羅漢の略称で、釈迦の弟子で最も位の高い人物です。
十六羅漢像や五百羅漢像を仏像として祀っている仏教寺院も多くあります。
また、祖師は仏教を世界に広めるために尽力した人物や、各宗教や宗派の創始者を指しており、弘法大師や鑑真和上像などが有名です。
仏像のポーズの種類と意味
仏像は、さまざまな手のポーズをしており、これを印相や手印と呼び、それぞれ意味が込められています。
施無畏印・与願印
施無畏印・与願印は、スタンダードな印相の一つで、2つセットで使われることがほとんどです。
奈良の大仏様はこの印相を結んでおり、施無畏印が相手の畏れを取り除くサイン、与願印が相手の願いを叶えるという姿勢を表現しています。
施無畏印は右手で、胸の前に構え中指を少し曲げたポーズ、与願印を表す左手は、上に向けて中指と薬指を少し上げたポーズをとっています。
仏像の中で一番有名な印相で、釈迦如来像によく見られるポーズです。
定印
定印も定番の印相の一つで、よく大日如来や釈迦如来坐像がとっているポーズです。
精神統一をして深い瞑想に入る姿を表現しているといわれており、禅定印と呼ばれることもあります。
両掌を上に向けて、左手の上に右手を重ね合わせ、親指の先を合わせたポーズが定印です。
阿弥陀如来の定印では、人差し指と親指をくっつけて輪を作るようなポーズをしています。
鎌倉大仏は、定印を結んでいます。
智拳印
智拳印とは、金剛界大日如来だけが表現できる特別な印相で、最高の智慧を意味しているといわれています。
胸の前で左手を握り人差し指を立て、その指を右手で包むようなかたちで握るポーズです。
インドでは清浄の手とされている右手が仏を表し、不浄の手とされている左手が衆生を表しており、智拳印は、仏の智慧が衆生を包み込んでいる様子を表現しているそうです。
来迎印(摂取不捨印)
来迎印とは、阿弥陀如来特有のポーズで、人が亡くなったときに阿弥陀仏が西方極楽浄土から迎えにくるときの印相です。
かたちは施無畏印・与願印に似ていますが、来迎印は親指と人差し指で輪を作る部分が異なります。
来迎印は、生前の行いによって9つのランクに分けられているといわれています。
また、浄土真宗では、来迎印を摂取不捨印と呼んでおり、どのような状況でも人々を収め取って見捨てないという阿弥陀仏の慈悲の心を表しているそうです。
説法印(転法輪印)
説法印は、転法輪印とも呼ばれ、お釈迦様が仏教についてジェスチャーを交えながら説法している姿を表したものです。
右手は立てて、親指と人差し指で輪っかを作り、左手は掌を上に向けた状態で親指と中指で輪っかを作り、両手を胸の前に近づけたポーズです。
釈迦如来や阿弥陀如来など、如来に多く見られる印相といえます。
降魔印(触地印)
降魔印とは、お釈迦様が悟りを開こうとして悪魔の妨害を受けたとき、邪魔をしてきた悪魔の集団を降伏させ、退散させた印相です。
右手の人差し指の先で地面に触れるようなポーズでもあるため、触地印とも呼ばれています。
日本の仏像では、奈良県の東大寺にある弥勒仏坐像が降魔印のポーズをとっています。