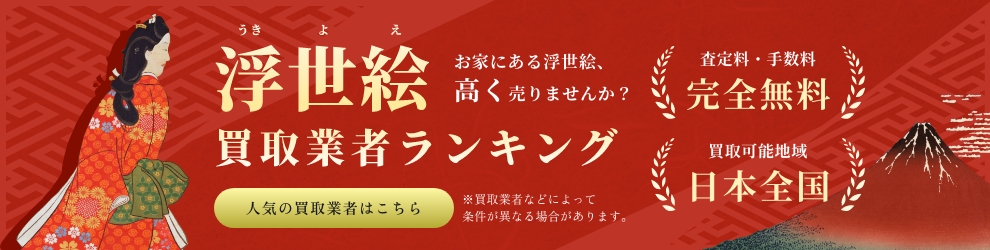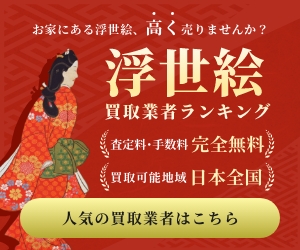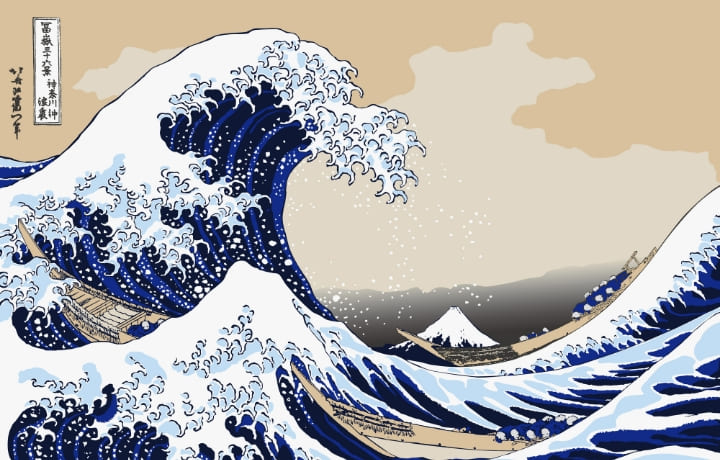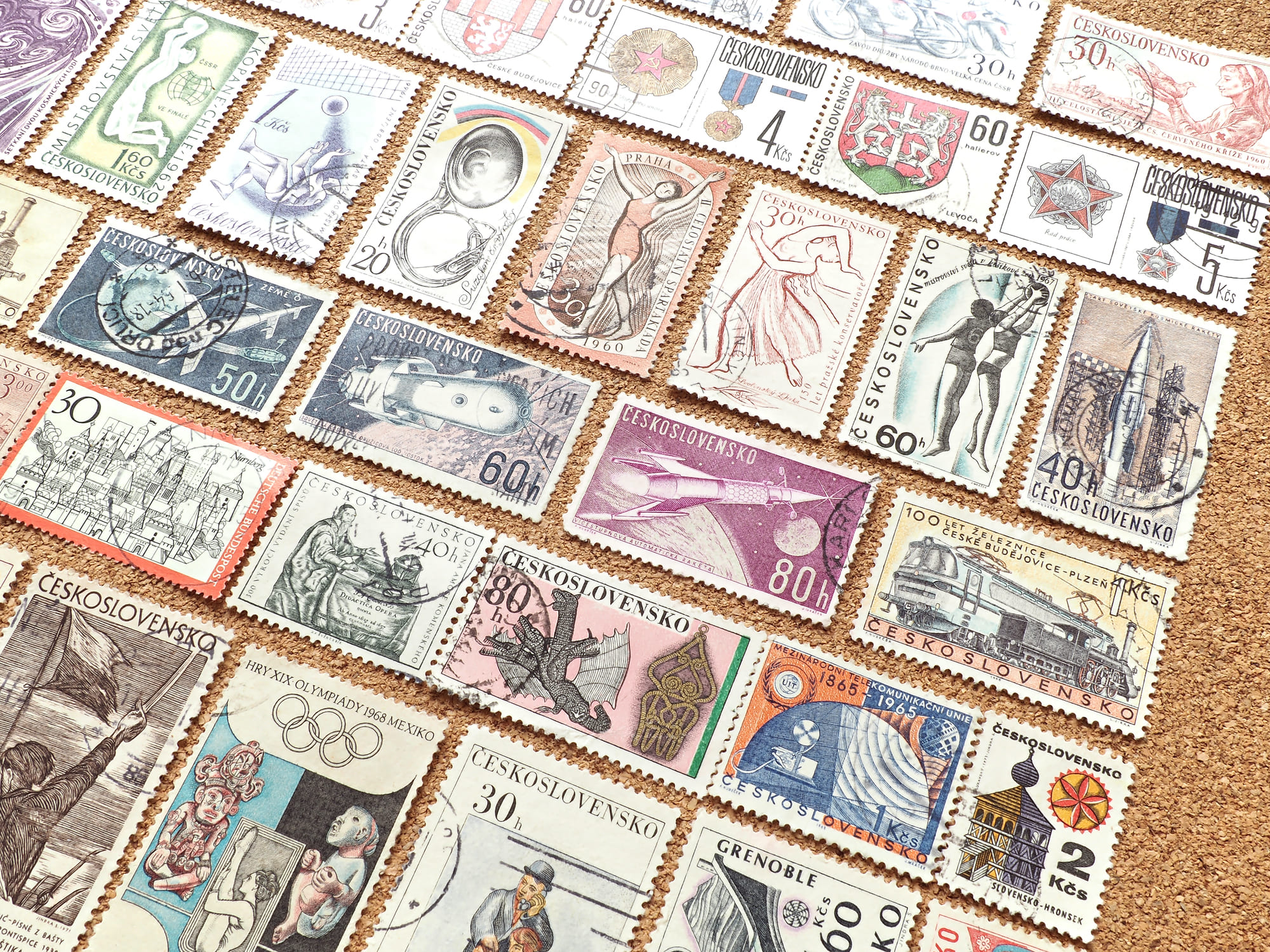浮世絵は日本を代表する伝統的な美術品であり、海外でも人気です。
そのため、浮世絵を買取に出すと高く売れるのではないかと期待されている方もいるでしょう。
しかし、浮世絵の種類によっては期待するほどの金額にならないかもしれません。
長年保管していた古いものであっても、ほかの骨董品と比べるとたいした買取価格ではないのです。
一方で、なかには高額をつける浮世絵もあります。
つまり浮世絵は、作品によって買取価格が大きく異なるのです。
目次
ほかの骨董品と比べて浮世絵作品はなぜ安い?
浮世絵が庶民の間で人気だったのは、江戸時代のこと。
その時代に制作された骨董品であれば、かなり古いもののため高額で取引される可能性が高いでしょう。
しかし、浮世絵の場合は、次のような理由からあまり高額での取引が期待できません。
全世界にコレクターがいる現在でも、ほかの骨董品と比べて浮世絵は高額買取されにくいのです。
「木版画」の技術により同じ絵をたくさん制作できたため
浮世絵は元々、浮世絵師が1点ずつ描く絵画でした。
このような肉筆による浮世絵は、江戸時代はもちろん、現在でもとても高額です。
しかし、その後「木版画」の技術が発達し、浮世絵師が描いた原画を使ってたくさんの浮世絵を制作できるようになりました。
浮世絵師が描いた浮世絵を原画として彫師が木の板に木版画を彫り、摺師が紙に印刷するといった流れができあがり、同じ絵柄の浮世絵を大量生産できるようになったのです。
同じ絵柄の浮世絵がたくさん出回るようになると、1枚ずつの価格は下がっていきます。
江戸時代、庶民の間で流行った浮世絵は基本的に大量生産されたものだったのです。
江戸時代当時も庶民が手に取りやすい価格だった
江戸時代に庶民の間で大流行していた浮世絵は、庶民にとって手軽に購入できる金額で販売されていました。
一般的に8〜20文ほどで取引されており、大判のものは20文ほどしたものの、現在のブロマイドともいえる「役者絵」は8文ほどだったようです。
かけ蕎麦1杯が約16文だったため、贔屓の役者の役者絵ならかけ蕎麦の半額で購入できたことになります。
江戸中期〜後期の貨幣価値 を現在に直すと、1文は10〜30円くらいです。
物価は時期によっても変動しますが、浮世絵1枚が数百円ほどで購入できたと考えてよいでしょう。
浮世絵が高く売れる条件
高額での買取があまり期待できない浮世絵ですが、条件によっては高額で取引されるケースもあります。
例えば以下のような浮世絵の場合、保存状態が良いものであれば1,000万円を超える可能性もあるのです。
ただ、浮世絵の真の価値を見極めるには専門家でなくては難しいでしょう。
自宅に眠っている浮世絵があれば、まずは専門家に相談することをお勧めします。
肉筆浮世絵であるか
浮世絵は、木版画で制作されているものが一般的です。
しかし、なかには浮世絵師が実際に筆をとって描いた「肉筆の浮世絵」があります。
このような肉筆浮世絵は、この世に1点しか存在しない非常に価値のあるものです。
そのため、大量生産できる木版画の浮世絵よりも高く売れるでしょう。
木版画の浮世絵が有名な歌川広重 や葛飾北斎 らも肉筆浮世絵を描いており、作品によっては高額で買取される可能性があります。
お手元にあれば、ぜひ査定を受けてみてください。
木版画でも初版であるか
木版画は何枚も摺れますが、何度も摺っている間に元の版木が擦り減ってきます。
そうなると、浮世絵の線がぼやけてしまったり、場合によっては一部が欠けてしまったりします。
そのため、同じ浮世絵であっても仕上がりが一番きれいなのは「初摺り」と呼ばれる初版です。
さらに初版の浮世絵に関しては、仕上がりの色合いなどを浮世絵師自らが指定しチェックしていました。
このような経緯から、木版画であっても初版の浮世絵は高額です。
有名な浮世絵師の作品であるか
江戸時代から明治時代にかけて浮世絵はとても流行しており、浮世絵師もたくさんいました。
残念ながら現在まで名の残っていない浮世絵師もおり、そのような絵師の描いた浮世絵は高額になりにくいでしょう。
一方で、有名な浮世絵師の作品であれば高額買取が期待できます。
『富嶽三十六景』の葛飾北斎や『東海道五十三次』の歌川広重、猫好きにはたまらない『猫飼好五十三疋』 を描いた歌川国芳などの作品であれば、需要があるため高額になりやすいでしょう。