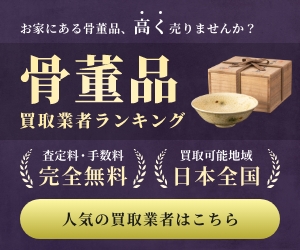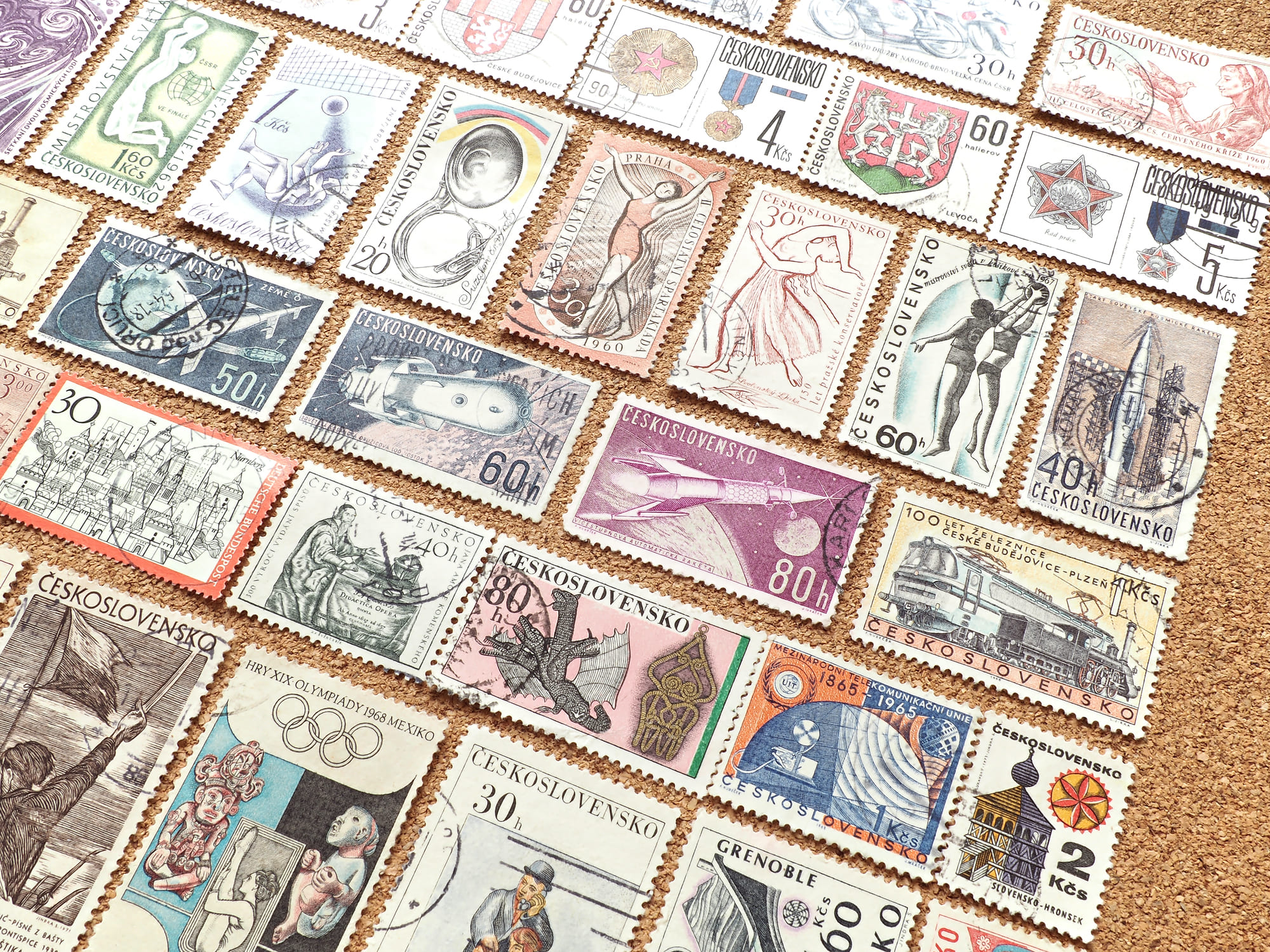自在置物とは
自在置物とは、日本の金属工芸の一つで、鉄や銅、銀、金と銅の合金、銀と銅の合金などの金属板を素材に、龍や蛇、鳥、エビ、伊勢海老、蟹、蝶などの動物の模型を指します。
単に、写実的に作成するだけではなく、体節や関節の部分を本物のように動かせることも追求しており、内部の仕組みが複雑になっているのも特徴の一つです。
たとえば、蛇の自在置物であれば、円筒型のパーツを数百個組み合わせており、とぐろを巻かせたり、流線型を描いたりと、自在に形を変えられる魅力があります。
自在置物は、日本よりも海外で高い評価を受けており、1888年にフランスで出版された日本美術の紹介雑誌『Le Japon Artistique』にて紹介されています。
自在置物の起源
自在置物は、明らかになっていないことも多いですが、起源は江戸の中期ごろです。
当初は、関東を中心に制作されていましたが、その後、北は弘前、南は高知と分派が全国各地に広がっていきました。
自在置物は、大名の手土産にするために制作されるようになったのではないかといわれています。
甲冑師が、武具や防具を受注するために、大名に自在置物を贈り、技術の高さをアピールしていたそうです。
自在置物を製作する甲冑師
戦国の世が終わりを迎え、平和な時代が訪れた江戸時代、武具類の需要が減少したことを受け、甲冑師の一部は技術伝承と収入を得るために、本業である甲冑だけではなく、鍔や轡などの武具、馬具、火箸、花瓶、箱といった民具を鉄で造り販売するようになりました。
自在置物は、この流れを受けて、室町時代から続く名家である明珍派の工人たちによって生み出された作品です。
明珍派の工人は、鉄を打ち出して加工する技術に長けており、自在置物の複雑な仕組みや繊細な表現が活かされています。
日本で作られる金工作品の写実性が向上するのは、江戸時代後期ごろからですが、自在置物の誕生は、それよりも早いといわれています。
お土産として人気となる
来日した西洋人が自在置物に興味を持つようになり、お土産物として人気を集めるようになりました。
日本人が得意とする繊細な細工の自在置物は、西洋人の心を魅了したといえるでしょう。
そして、明治時代に入ると、廃刀や西洋式生活が導入されるようになり、甲冑師や金工の職人たちは職を失ってしまいました。
そのような時代背景があり、職人は自在置物を盛んに制作するようになりました。
外交官の佐藤尚武が駐在先のフランスに、お土産として高瀬好山の工房で制作された置物を贈ったところ、評判がよかったため、追加注文を出したという話があるほど、海外でも人気のある工芸品です。
現在の自在置物
現在も、京都で金工を仕事にしていた冨木伊助や、伊助から金工を学んだ高瀬高山の作品が残されています。
高山は、金沢生まれで、神戸の貿易会社に勤めていた経験があり、販売経営で優れた才能を発揮していたそうです。
1893年に京都で独立したのち、明治の終わりには皇太子殿下の御買上げに預かり、昭和の初めまで、さまざまな展覧会に作品を出品しています。
当時需要が高かったため、制作が追い付かなくならないよう、工房制作の体制を取っていました。
現在、自在置物を制作している人物は、2人のみといわれています。
1人は、伊助の子孫にあたる冨木宗行で、2人目は、宗行の弟子である満田晴穂です。
「自在置物」が定着し、認知度も上がる
伝統工芸品である自在置物の名称は、比較的新しい時代に作られています。
東京国立博物館が明治時代の終わりに購入した里見重義作の銀製の龍の箱に、『純銀製自在 龍』と書かれていました。
当時の台帳には『自在龍置物』と登録したため、1983年に博物館で特別展を開催した際に、同じような作品に「自在○○置物」と名づけ、自在置物という言葉が用いられるようになったといえるでしょう。
木製の自在置物
基本的に、自在置物は、鉄や銀、銅などの金属で制作されていますが、木を用いて制作された自在置物作品もあるのです。
接合部分は、はめ込む仕組みになっており、制作する生き物の動きによって割れたり欠けたりしないよう、高い技術が必要です。
また、木で制作される自在置物も、写実性が高く本物にそっくりな魅力があります。