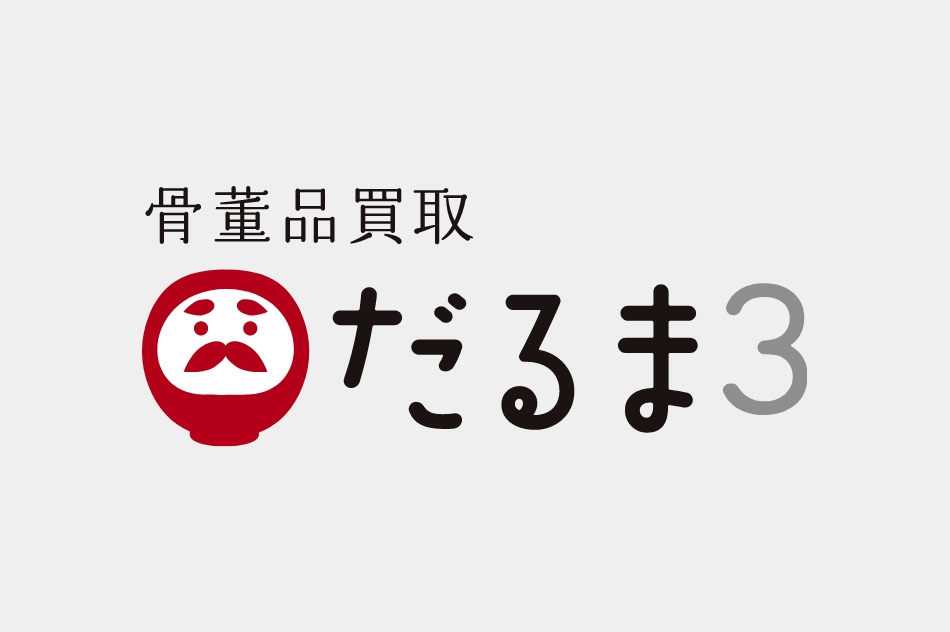皆さんは、月岡芳年(1839年-1892年)という画家を知っていますか?
もし、江戸時代の浮世絵を代表するのが「葛飾北斎」や「歌川広重」なら、明治を代表する浮世絵師としては、間違いなく「月岡芳年」の名が挙がるでしょう。
芳年は、残酷な戦場や戊辰戦争をテーマにした浮世絵を多く残しており、時には「血まみれ芳年」と呼ばれることも。
一方で、幅広いテーマで絵を描いており、幕末から明治期の浮世絵界をけん引した人物でもあるのです。
-1024x768.jpg)
今回は、町田市立国際版画美術館で開催中の「明治時代の歴史物語―月岡芳年を中心に」を訪れ、芳年の作品世界と彼の生涯に迫ります。
![「明治時代の歴史物語―月岡芳年を中心に」ポスター [引用元:町田市立国際版画美術館 公式HP]](https://daruma3.jp/kottouhin/wp-content/uploads/2024/11/「明治時代の歴史物語―月岡芳年を中心に」ポスター-[引用元:町田市立国際版画美術館-公式HP].jpg)
目次
「明治時代の歴史物語―月岡芳年を中心に」は町田市立国際版画美術館にて開催中
-225x300.jpg)
「明治時代の歴史物語―月岡芳年を中心に」は、町田市立国際版画美術館で開催されている展示会です。
町田市立幕末から明治期にかけて活動した浮世絵師・月岡芳年の作品に焦点を当て、彼の描いた「歴史」にまつわる浮世絵の世界を紹介しています。
この企画展では、明治政府の国家観や古事記に登場する神話の人物、忠義を尽くす賢臣たちを題材にした芳年の作品が多く見られます。
また、晩年の作品には、幽玄な雰囲気が漂う講談や謡曲を基にした描写が含まれ、静と動の表現を駆使し、多くの人々を魅了する芳年の画風が存分に堪能できるでしょう。
展示には芳年の弟子である水野年方や右田年英、また芳年に私淑した小林清親などの作品も展示され、芳年が後進に与えた影響も垣間見える内容となっています。
この展示は、2024/9/13~2024/12/1まで開催されており、明治時代の芸術と歴史の奥深さを堪能できる貴重な機会です。
今回の、企画展は町田市立国際版画美術館の2階「常設展示室」で行われているものになります。
なんと入場無料のため、どなたでも気軽に月岡芳年の作品を楽しめます!
普段、浮世絵を観る機会がないという方も、ぜひ気軽に足を運び、浮世絵のそして歴史絵画の魅力を味わってみましょう。
大充実の展示で、明治時代の作品を堪能
-300x225.jpg)
今回訪れた「明治時代の歴史物語―月岡芳年を中心に」は、なんといっても入場無料で鑑賞できるのが大きな魅力です。
また、展示室内の撮影も可能となっており、写真を撮影してあとから振り返りもできます。
鑑賞中のマナーについて書かれた案内をよく読み、大きなシャッター音やフラッシュ撮影、三脚を使用した撮影などは、ほかのお客さまの迷惑にもなるため控えましょう。
-1024x768.jpg)
常設展示室は正方形の部屋で、壁一面に月岡芳年の作品がずらりと並ぶシンプルな作りの企画展でした。
シンプルであるからこそ、一つひとつの作品をじっくりと鑑賞できますね。
-768x1024.jpg)
展示室内入ってすぐの壁面には、月岡芳年と今回の企画展を紹介する文章が展示されています。
こちらをしっかりと読み、一つひとつの作品を堪能していきましょう。
作品数は前期・後期それぞれ35点あり、すべて入れ替えとなるため時期をずらして2度訪れれば、70点もの作品を鑑賞できます。
無料の展示会でありながらもボリュームがあり、月岡芳年好きには堪らない展示会ですね。
テーマに沿って描かれた作品が勢ぞろい
今回の展示では、月岡芳年の代表的シリーズ「大日本名将鑑」「新形三十六怪撰」「月百姿」など、彼の多彩なテーマ作品がそろい、まさに芳年の創作の幅広さを実感させるものでした。
芳年は、生涯で約1万点の作品を手がけ、同じテーマでも多くの作品を生み出したことから、各テーマごとに描かれた絵を比較しながらの鑑賞も楽しめ、一つひとつの作品だけで見るときとはまた違った発見ができる魅力もあります。
芳年の作品テーマは500ほどあり、同じテーマ内において複数の作品を制作しており、中には同じテーマで100点の作品を描いているものもあるそうです。
江戸時代から続く浮世絵の美しさとともに、複数のテーマで繰り返し制作する芳年の姿勢から、歴史や物語に対する芳年の深い愛着と探究心がうかがえますね。
大日本名将鑑:武者絵シリーズ
-1024x768.jpg)
大日本名将鑑は、1877年ごろに制作された全51図におよぶ通史的な武者絵シリーズです。天照大神から徳川家光まで、神話や歴史上の偉人たちが描かれ、源頼朝や足利尊氏などの中世武将、また織田信長や徳川家康といった近世の名将もテーマとなっています。
また、神武天皇や日本武尊といった古代皇族も含まれており、1872年に明治政府が尊皇愛国思想の教化を促進していたことが関係しているといわれています。
芳年は、天皇の正統性を視覚的に示す作品を通して教育的意図も込めたと考えられているのです。
また、画風においては写実性や陰影を生かした西洋画の影響が随所に表れています。
構図にも工夫が凝らされており、人物の斜めや背後からの姿勢を巧みに表現し、彼のデッサン力が光る作品に仕上がっています。
また、かつて「血みどろ絵」で知られた芳年ですが、このシリーズでは残酷表現が見られず、武将たちの壮麗さを前面に出している点が、また違った魅力です。
-1024x768.jpg)
『天照皇大神』1882年/大判錦絵
『天照皇大神』は、1882年に制作された作品で、有名な天岩戸伝説をテーマにした大判錦絵です。
この作品では、太陽神である天照大神が弟の素戔嗚尊の横暴に怒り、天岩戸に隠れてしまった様子が描かれています。
天照大神が隠れたことで、世界は暗闇に包まれ、神々は困り果てます。
そこで、彼らは岩戸の前で宴を開き、天宇受売命が舞を踊って天照大神の興味を引きつけ、岩戸から顔を出した瞬間を見逃さず、天手力雄神は岩を動かして天照大神を外に出すのです。
この作品では、まさに天手力雄神が岩を動かして、天照大神の姿が外に出る瞬間を描いています。
岩戸の内側と外側のコントラストが強調されている点が目を引きます。
古代の神々の話ではありますが、感情やドラマがリアルに感じられるとともに、明暗のコントラストから天照大神の存在がいかに重要であるかが分かる作品ですね。
新形三十六怪撰:妖怪画シリーズ
-1024x768.jpg)
新形三十六怪撰は、幕末から明治初期にかけて活躍した芳年による妖怪画の連作で、1889年に刊行が開始され、1892年に完結しました。
全36点から構成されるこの作品は、古来の妖怪を新しい感覚で描写した点が特徴です。「新形」という題名には、妖怪の新たな表現を意味するほか、「神経」に掛けているとも考えられています。
画面の枠が虫食い状にデザインされているのは、劣化を示すものではなく、芳年の神経異常を反映した幻覚を表しているという説が。
妖怪画であるにもかかわらず、多くの作品では妖怪そのものよりも、それらを見る人間の姿を中心に描いています。
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
たとえば、『仁田忠常洞中に奇異を見る図』や『業平』では、妖怪を見る人間だけが描かれていますね。
-300x225.jpg)
また、『清盛福原に数百の人頭を見るの図』では、襖の取っ手と月が重なり、髑髏のように見えるように描いており、隠し絵のような楽しみ方も。
妖怪や怪異を隠し絵のように表現することで、人間の妄想であるかのような解釈ができるよう意図されているのです。
-1024x768.jpg)
『小早川隆景彦山ノ天狗問答之図』1892年/大判錦絵
『小早川隆景彦山ノ天狗問答之図』は、1892年に制作された作品で、天狗と対峙する小早川隆景を描いた大判錦絵です。
画面の左側には、緑の直垂姿で立つ隆景が描かれており、右側には山伏の姿をした天狗が堂々と立つ様子が描かれています。
作品全体に引かれた筋は、天狗が起こした突風を象徴しており、自然の力が表現されています。
この作品は、神木を伐採しようとする隆景と、それを戒める天狗との対話の様子を描写しています。
突風のすき間からしか姿は見えませんが、聡明であった隆景が一歩も引かず、天狗と対峙している姿勢は非常に印象的です。
彼の毅然とした態度は、無謀とも勇気とも捉えられる心情の狭間で揺れ動く人間の姿を象徴しているように感じられます。
この作品からは、自然との共存や神々の力の強大さについても深く考えさせられますね。
芳年の独特な画風が、天狗の堂々たる姿を強調しており、観る者に強いメッセージを与えてくれます。
月百姿:歴史画シリーズ
-300x225.jpg)
月百姿は、1885年から1891年にかけて発表された浮世絵の揃い物作品です。
このシリーズは、日本や中国の物語、伝承、歌舞伎をテーマにした「月」に関連する100の歴史的な絵です。
月岡芳年は、武将や美人、幽霊、怪物、動物など、さまざまな主題を描き出し、その多様性が大きな魅力となっています。
月百姿では、月の表現も満月や三日月、半月に加え、戦国武将の甲冑の前立としての三日月など、主題に応じて多彩に変化します。
写生に強いこだわりを持つ月岡芳年の作品は、写実性とともに幻想的な雰囲気を醸し出し、観る者を惹きつけているのです。
背景に関しても、シンプルな構図から月を主題と同じサイズで描く斬新な手法まで、さまざまなアプローチが見られ、100図それぞれが独特の個性を持っているのが見どころです。
月百姿は、月岡芳年の人生の集大成ともいえる作品であり、彼の浮世絵師としての技術が余すところなく表現されています。
-300x225.jpg)
『貞観殿月』1888年/大判錦絵
1888年に制作された『貞観殿月』は、弓の名手である源経基が一矢で鹿を仕留める瞬間を描いた大判錦絵です。
芳年の他の作品『大日本名将鑑』の六孫王経基と同様、経基の鹿退治をテーマにしています。
こちらの作品では、経基が後ろ姿で描かれ、彼が弓を放った一瞬を捉えることに重きを置いています。
後ろ姿ではありますが、弓を放った瞬間の躍動感ある佇まいから、経基の力強さや集中力の高さを感じさせてくれますね。
弓を引く瞬間の緊張感が際立っており、大きな絵ではありませんが迫力を感じました。
また、同じテーマを扱った『大日本名将鑑』の六孫王経基と見比べると、月岡芳年の異なる視点や技術の変化を楽しめます。
門下の水野年方・右田年英・尾形月耕・小林清親らの作品も展示されている
「明治時代の歴史物語―月岡芳年を中心に」では、月岡芳年の作品だけではなく、明治時代に活躍した水野年方・右田年英・尾形月餅・小林清親らの作品も展示されています。
水野年方の作品は、前期に『楠正行弁の内侍を救ふ図』、後期に『本多忠勝小牧山軍功図』が展示され、右田年英は英雄三十六撰シリーズ、尾形月耕は月耕随筆、小林清親は小学日本略史などの作品が展示されています。
月岡芳年の作品とともに鑑賞して、日本の歴史を眺めるとともに、浮世絵師ごとの特徴の違いに目を向けてみるのもよいですね。
共通点を見つけてみたり、違いを発見してみたりと、さまざまな楽しみ方ができます。
充実のグッズを見るのも楽しみの1つ:企画展限定のものも!
町田市立国際版画美術館のミュージアムショップでは、図録や美術関連書籍に加え、和雑貨や缶バッジ、町田のお菓子、創作絵本など、さまざまなアイテムを取り揃えています。
特に企画展に合わせた期間限定グッズも見逃せません。
おすすめは、ここでしか手に入らないオリジナルの絵葉書やメモ帳などのグッズです。
アートや文化に触れながら、特別なアイテムを見つけてください。
明治時代を盛り上げた浮世絵師・月岡芳年の作品を鑑賞できる「明治時代の歴史物語―月岡芳年を中心に」
-300x225.jpg)
今回、町田市立国際版画美術館で開催中の「明治時代の歴史物語―月岡芳年を中心に」を訪れた感想を紹介しました。
本企画展では、歌川国芳の弟子であり、血みどろ絵で有名な月岡芳年の浮世絵作品が楽しめます。
無残絵が有名な芳年ですが、実は妖怪画や歴史画、武者絵などもたくさん描いているのです!
今回の企画展では、無残絵の印象を強く持っている人たちにとっては、芳年の新たな一面を発見できるのではないでしょうか。
今回の展示を通して、芳年の多彩な才能に触れてみるのもよいでしょう。
-300x225.jpg)
また、町田市立国際版画美術館にはドリンクと軽食が楽しめる「喫茶けやき」があります。
日本橋に本店を持つ「ミカド」のコーヒーやケーキを楽しめるとともに、人気のグリルサンドや、季節ごとの旬の食材を使用したパフェ、企画展に合わせた期間限定メニューなど、手作りの豊富なメニューがそろっています。
店内から見える芹ヶ谷公園の緑は、季節ごとに変化し、訪れる人々に癒しを与えてくれるでしょう。
企画展鑑賞後は、月岡芳年が描いた作品の余韻を味わうとともに、おいしいコーヒーやケーキを楽しむのもおすすめです。
開催情報
『明治時代の歴史物語―月岡芳年を中心に』
場所:〒194-0013 東京都町田市原町田4-28-1
期間:2024/9/4~2024/12/1
公式ページ:https://hanga-museum.jp/
チケット:入場無料
※詳細情報や最新情報は公式ページよりご確認ください

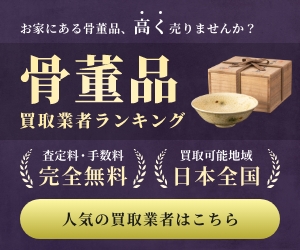






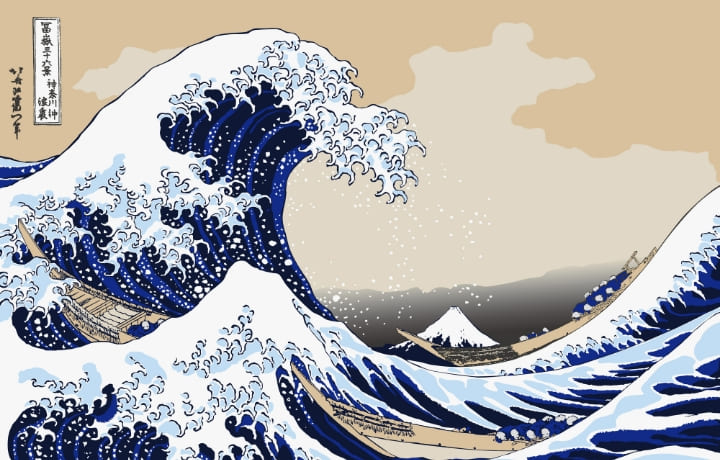



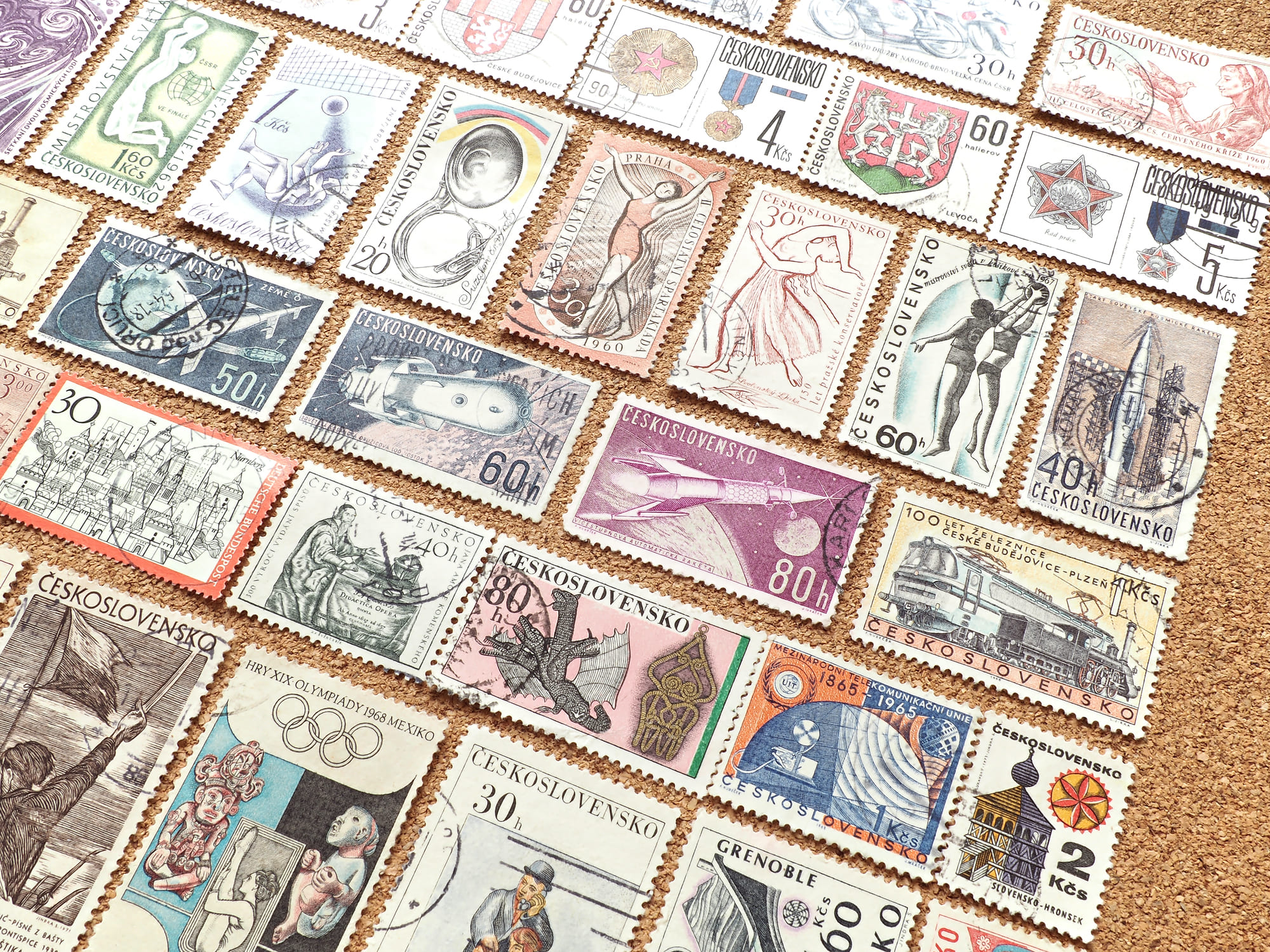



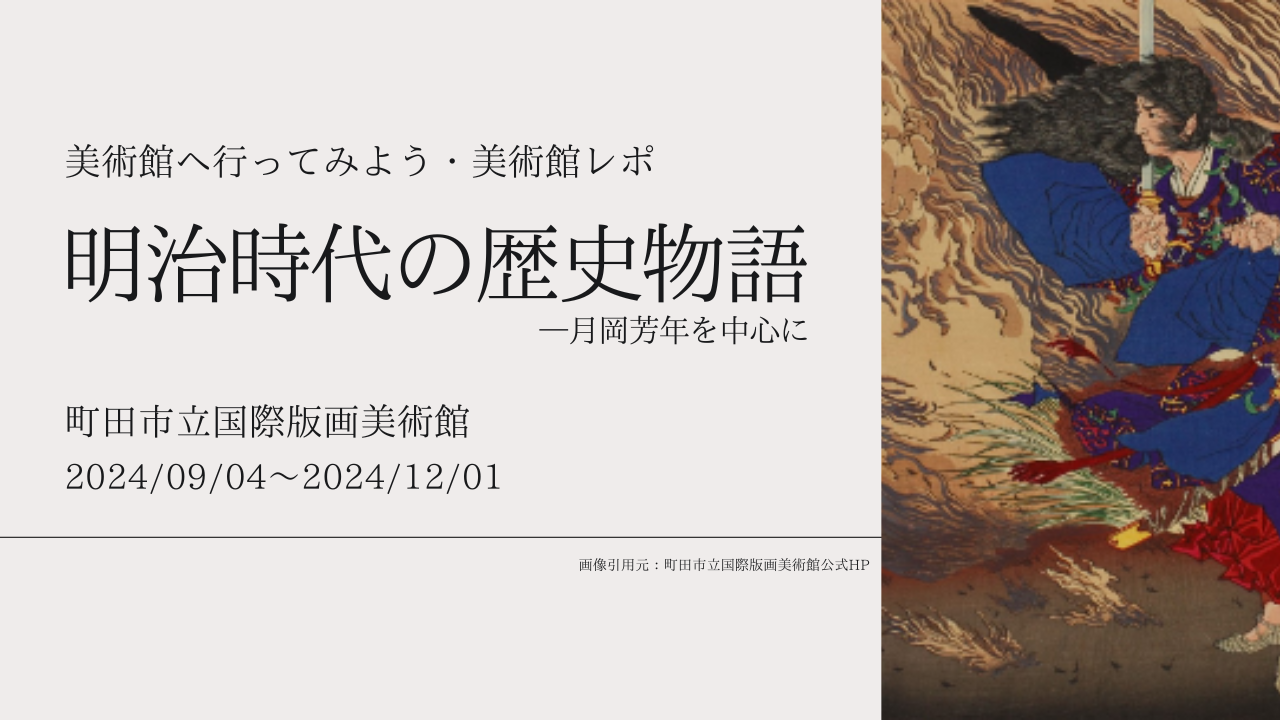
.png)