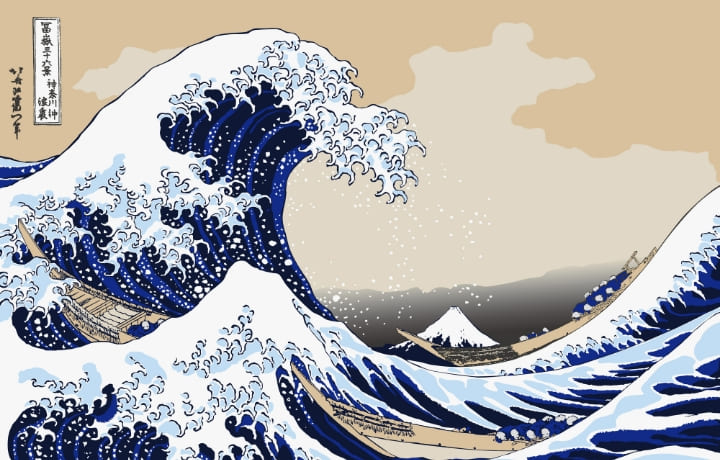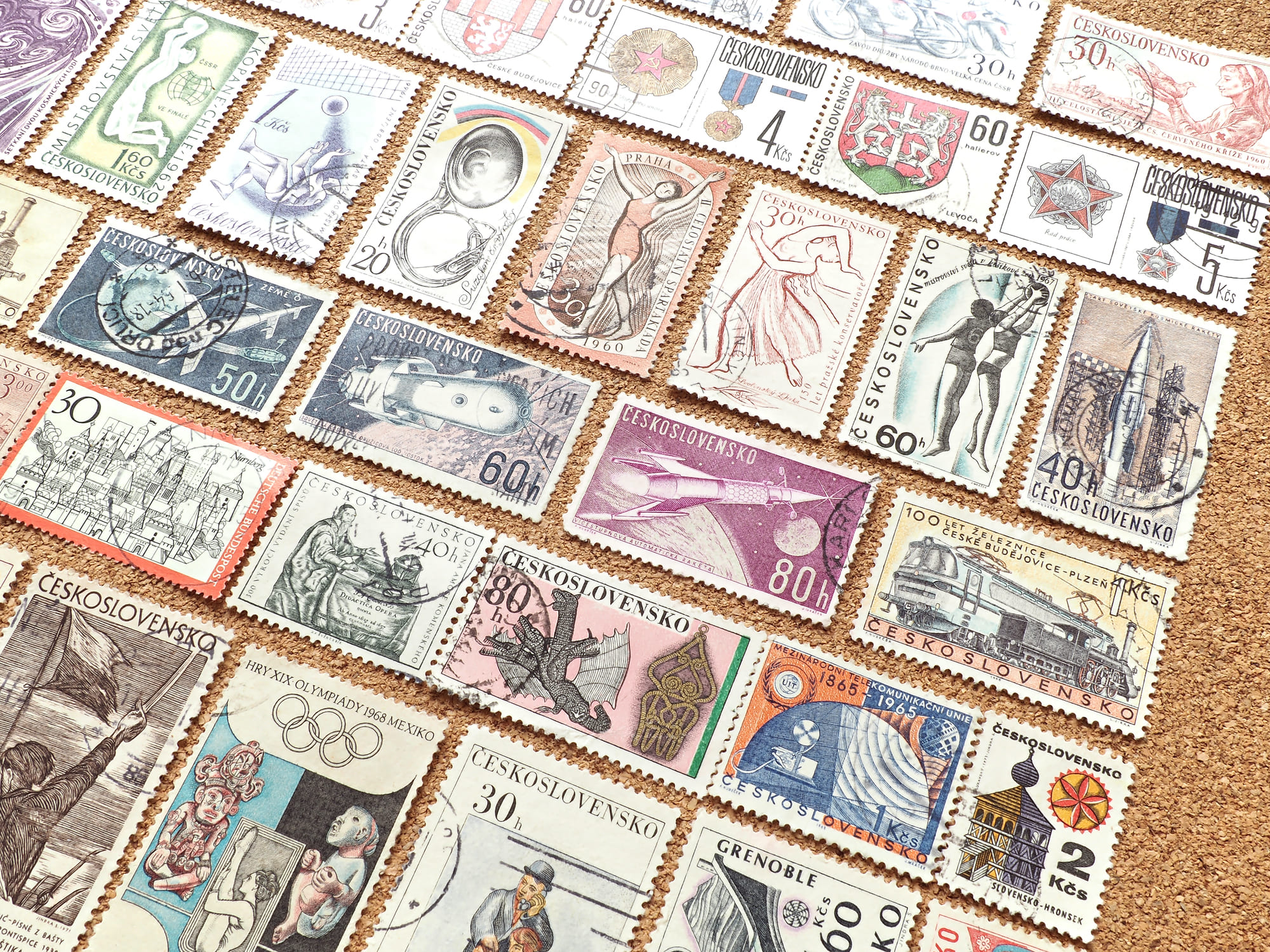-
.png)
「TORIO」展…3つ並べてみる感動と新たな発見 | 大阪中之島美術館
パリ・東京でも大人気だった「TORIO」展、大阪でも開催中 大阪中之島美術館で開催中の「TRIO パリ・東京・大阪 モダンアート・コレクション」展は、パリ、東京、大阪の3都市を代表する美術館のコレクションが一堂に会する展覧会。 この展覧会の最大の魅力は、各美術館のコレクションから厳選された作品が34のテーマに基づいてユニークなトリオ形式で展示されている点です。 20世紀から現代に至るまで活躍した日本と西洋のアーティスト総勢110名による約150点の作品が展示されており、その中には初来日となる32点の作品も含まれています。 モダンアートを象徴する巨匠たちから、現代の気鋭アーティストまで、幅広い作家の作品を一度に楽しめる貴重な機会といえるでしょう。 この展覧会は、パリ、東京、大阪の学芸員が1年以上にわたって自由な発想で議論を重ねて構成したもので、アート初心者から熱心なファンまで「見る」「比べる」「語る」という楽しさを私たちに提供してくれます。 大阪中之島美術館は、構想から40年・2022年に開館したばかりの新しい美術館。大阪にある美術館のなかでも最大級の広さで、国内外の作品を数多く展示しています。また、写真には写っていませんが、美術館前の定番写真としてよく撮影されているのは、ヤノベケンジによる作品『SHIP'S CAT(シップス・キャット)』。大阪中之島美術館のシンボルともいえるアート作品ですので、ぜひ見てみてくださいね。 https://daruma3.jp/kottouhin/381 時間も場所も超えて…魅力的な作品たちが展示されている「TORIO」展 私たちを迎えるのは、佐伯祐三の『郵便配達夫』を含む3作品 佐伯祐三 作品名:『郵便配達夫』 制作年:1928年 中之島美術館がオープンしたときにも展示されていた『郵便配達夫』(佐伯祐三)を含む3作品がお出迎え。 大阪に住んでいる方ならお分かりかもしれませんが、中之島美術館がオープンした2022年当初、この作品はポスターにも使用されていました。それもあってか、「ついに会えた!」という感動。 意図してかせずか、このはじまりに嬉しい驚きを覚えた来場者の方も多いのでは…!と思いました。 大阪の街並みにも出会える 展示作品には、大阪にゆかりのあるものもいくつかありました。 小出楢重 作品名:『街景』 制作年:1925年 たとえば、小出楢重の『街景』は、大正時代の大阪・中之島周辺を描いた作品。 ビルの上から見下ろす中之島の風景には、モダンな建物と工場の煙が眼下に広がり、商業の街として発展しつつある当時の大阪の様子が伺えます。 河合新蔵 作品名:『道頓堀』 制作年:1914年 また、大阪出身の河合新蔵も大阪の街を描いています。 この『道頓堀』では、現在はネオン輝く観光地となった大阪ミナミの中心地にかつてあった懐かしい光景が広がっています。 作品の新たなストーリーに出会えるのはTORIOだからこそ このほかにも、「TORIO」展ならではの視点で展示されたさまざまな作品を鑑賞することができます。 ダリやシャガール、ピカソ、岡本太郎などの誰もが知る有名画家の作品から、一般的には著名ではないかもしれませんが、独自の魅力が宿る作品まで、あらゆるTORIO作品を堪能できるのが、なんといってもこの美術展の魅力と言えるでしょう。 左: マリー・ローランサン 作品名:『プリンセス達』 制作年:1928年 中: 藤田嗣治(レオナール・フジタ) 作品名:『五人の裸婦』 制作年:1923年 右: ジャン・メッツァンジェ 作品名:『青い鳥』 制作年:1912-1913年 個人的に、特に感動したのが、マリー・ローランサンと藤田嗣治(レオナール・フジタ)を一緒に鑑賞できたこと。 美しく柔らかな曲線と陶器のような肌を持つ女性たちの絵を、こうして見ることができ、あたたかな幸福感を感じざるをえません。 ちなみに、この藤田嗣治(レオナール・フジタ)の『五人の裸婦』、実は人間の”五感”をあらわしているのだとか。 また、パリでの深い親交があったとされる岡本太郎の絵画と、ジャン・アルプの彫刻作品も、TORIO展では同じテーマの作品として楽しむこともできます。 「これはただ抽象ではないんだ。これらは生きているんだ。生活なのだ」 ― ジャン・アルプの言葉 (大阪中之島美術館:音声ガイダンス内での紹介) 抽象的でありながら、有機的な何かを感じさせる二者の作品をこうして同じ場所で鑑賞することができます。 パリ・東京・大阪を巡った「TORIO」展ももうすぐフィナーレ 普段ならなかなかお目にかかることのできない作品を、しかもこんなにたくさん鑑賞できるなんて、なんと贅沢な時間! 最終日まであとわずかのタイミングで来れたのは良かったですが、正直なところ「もっと早く来ておけば良かった…」というのが本音。 前期・後期で展示替えもあり、また、学芸員の方の解説が聞ける機会も何度かあったようで、もったいないことをしたな、と思いました。 しかし!ラッキーなことに、最終日間近ということで、グッズが少しお得になっていました。 セット価格で販売されている商品もありましたし、私は3,300円以上購入でもらえるミント缶をプレゼントしてもらいました。 https://daruma3.jp/kaiga/212 美術館の帰りは、近くのカフェで、目録やお気に入り作品のポストカードを眺めながらゆったりとしたひとときを過ごしました。グッズは、クリアファイルやポストカードなどの定番のものから、Tシャツやポーチ(3つの絵柄が現れる!)など実に多彩で、ついつい手に取ってしまいますね。 最終日まであとわずか! パリ・東京・大阪の3都市と、近代から現代までの時間を旅行したような満足感のある「TORIO」展は、大阪中之島美術館で開催中です。 開催情報 場所:大阪中之島美術館 期間:2024/09/14~2024/12/08 公式ページ:https://nakka-art.jp/exhibition-post/trio-2024/ チケット:一般 2100円 高大生 1500円 中学生以下 無料 ※詳細情報や最新情報は公式ページよりご確認ください https://daruma3.jp/kottouhin/441
2024.12.03
- すべての記事
- 美術展・イベント
- 大阪
-

海の宝石・珊瑚の装飾品や置物は高額買取が期待できる?!
海の宝石と呼ばれている珊瑚は、古くから祈祷や装身具として利用され、富や権力、生命力を象徴するものとして人々に大切にされてきました。 珊瑚は、色や産地によって種類が分類され、なかでも赤珊瑚と呼ばれる種類の珊瑚は、大変貴重で、高価買取が狙えるものとして注目を集めています。 珊瑚の買取依頼を検討中ですか? 現在、珊瑚は個体数が減少し、さらには採取規制がかかり希少性が大変高まっています。 珊瑚を所有している方で、処分に困っている方がいましたら、捨てる前にまずは査定に出してみるのがお勧めです。 見た目の美しさから、ジュエリーやアクセサリーとして実際に使用する人もいれば、コレクションして鑑賞を楽しむ人もおり、種類や状態によっては高価買取が期待できます。 珊瑚の価値を知りたい方は、専門の買取業者に相談してみましょう。 いつの時代も珊瑚は人気 珊瑚は、美しい色彩とツヤが魅力的な宝石で、古くから装飾品として親しまれてきました。 もともと地中海で採れていた珊瑚は、シルクロードを通して日本に伝わり、江戸時代以降から日本産の珊瑚が注目されるようになりました。 明治時代になると、主な産地であった高知県で原木のオークションが開催されるようになり、現在まで続く日本の宝石珊瑚産業の中心地となります。 現在も高知県には、伝統的な珊瑚の採取と加工の技術が伝承されており、土佐の職人が一つひとつ丁寧に磨き上げて作った宝石珊瑚は、世界的にも高い評価を受けています。 このように、珊瑚は古くから現在まで、多くの人々に親しまれてきたのです。 自宅に眠る珊瑚はありませんか 珊瑚は、年々産出量が減り希少性が高まっており、価格も高騰している宝石の一つです。 もし、自宅を整理していて珊瑚が出てきたり、相続で受け取った珊瑚が自宅にあったりする場合は、一度査定に出してみてはいかがでしょうか。 種類や品質によっては高額買取も期待できるでしょう。 アクセサリーをあまり身に付けない、自宅のデザインとマッチしないため飾る場所がない、など扱いに悩んでいる方は、査定をして価値を知り、買取に出すのも一つの手段です。 まずは一度、実績豊富な買取業者に相談しましょう。 高額買取が狙える珊瑚は? 珊瑚の評価や買取価格を決めるポイントは、形状や状態、付属品などです。 自宅に眠っている珊瑚にどのくらいの価値がつくのか事前に予測するためにも、高額買取が狙える珊瑚の特徴を知っておくとよいでしょう。 日本の珊瑚は価値が高い 日本産の珊瑚は、ほかの場所で採れた珊瑚よりも価値が高いとされています。 特に、高知県土佐湾で採れる血赤珊瑚は、世界中から高い評価を受けており、最高級品の珊瑚として取引されています。 また、日本近海で採れる桃色珊瑚も人気が高く、高価買取が狙えるでしょう。 ほかには、地中海の紅珊瑚、沖縄近海や東シナ海の白珊瑚も、比較的高値で取引されている珊瑚です。 日本産の珊瑚は、品質がよく高い評価を受けやすいため、お手持ちの珊瑚が日本産であれば査定に出して価値を調べてみましょう。 また産地が分からなくても、日本産の可能性はあるため、あきらめず専門家に見てもらうことをお勧めします。 形状がよいか 珊瑚は、原木のほかに、丸珠、半球(ラウンドカット)、カポションカットなどの形状があります。 10mm以上のサイズの丸珠は、大変希少性が高く、高価買取が狙える形状といえます。 また、宝石珊瑚の中には、彫りが施されているものもあり、芸術性の高さから、美術品や骨董品としての価値がプラスとなり、査定額が上がるものもあるようです。 ダメージが少ないか 珊瑚は、水や湿気、酸、熱に弱い性質をもっており、汗や酢、果汁などにも酸が含まれており、珊瑚にダメージを与える原因となります。 アクセサリーとしての珊瑚を気温の高い時期に身に付けていると、汗により劣化してしまうおそれがあります。 また、適切に保管できていないと変色してしまい、一度変色してしまった部分は元に戻せません。 表面のツヤがなくなった程度の場合は、研磨により輝きを取り戻せますが、変色は修繕ができないため、価値を大きく下げてしまう可能性があるでしょう。 付属品はそろっているか 珊瑚には、鑑定書や産地証明書が付属している場合があり、セットで査定に出すとプラスの評価をつけてもらえるケースがあります。 また、ブランド品の宝石珊瑚であれば、ギャランティカードや購入時の包装もとっておくと査定でプラスに働く可能性があるでしょう。 作られた年代が古いものは、歴史的価値や美術品的価値があるものも多く、箱や箱の表書きがあれば査定額がアップする場合もあります。 珊瑚を購入したり譲り受けたりした際の付属品は、すべて捨てずにとっておくようにしましょう。 珊瑚を手放すとき、どんな方法がある? 珊瑚を手放したいと考えていても、どのような方法があるか分からない方も多いでしょう。 珊瑚を手放す方法の種類と特徴を知り、自分にあった方法で手放せるようにするのがお勧めです。 ネットオークションやフリーマーケットで売却 珊瑚は、ネットオークションやフリーマーケットでの売却が可能です。 自分で自由に価格を設定できるため、希望価格やそれ以上の価格で販売できるメリットがあります。 珊瑚の価値を把握している場合は、価格設定で損をすることが少なくなるため、お勧めの方法です。 ただし、珊瑚の正しい価値を知らない場合、本来の価値よりも低い価格をつけてしまい、損をしてしまう可能性があります。 また、ネットオークションであれば自分で出品・配送などの手続きを行う必要があるため、慣れていないと手間に感じるでしょう。 フリーマーケットでは、直接お客さんとコミュニケーションを取りながら販売するため、時には値下げ交渉をされるケースもあるため注意が必要です。 リサイクルショップで売却 リサイクルショップでも、珊瑚の買取を受けてくれる場合があります。 店舗に持ち込んで最短即日売却が可能なため、できるだけ早く売却してお金を受け取りたい場合にお勧めの方法です。 しかし、リサイクルショップの店員が、珊瑚の価値に詳しいとは限らないため、適切な価格をつけてもらえない可能性があります。 自分自身も価値を把握していなければ、大きく損をしてしまうおそれがあるでしょう。 不用品回収業者や遺品整理業者へ相談 不用品回収業者や遺品整理業者は、複数のものをまとめて引き取ってくれるため、遺品整理で珊瑚のほかにも回収してほしいものがたくさんある場合に便利な方法です。 しかし、まとめて買取となるため、1点1点の価値を確認しづらく、本来よりも低い価格で珊瑚を買い取られてしまう可能性があります。 骨董品買取業者へ相談 適切な価格で珊瑚を売却したい場合は、珊瑚に関する専門知識をもつ査定士のいる骨董品業者の利用がお勧めです。 専門家が査定してくれるため、価値に見合った買取額をつけてもらえる可能性が高いでしょう。 ただし、業者によって買取実績は異なるため、骨董品全体の実績だけではなく、珊瑚の実績があるかどうかを事前にチェックしておくのがお勧めです。 査定は無料で実施している業者も多いため、複数の業者に査定を依頼して比較するのもよいでしょう。 珊瑚を高額買取してもらうためのチェック項目 大切な珊瑚を手放すなら、なるべく高値で買い取ってもらいたいと感じる人も多いでしょう。 お手持ちの珊瑚が高価買取の対象となるか判断するためには、種類・カラー・フラクチャーなどをチェックする必要があります。 種類 代表的な珊瑚の種類には、赤珊瑚、紅珊瑚、桃色珊瑚、白色珊瑚などがあり、種類によって高価買取を狙えるかが異なります。 色味の濃い赤珊瑚は、人気が高く高額で取引されやすい種類の珊瑚です。 黒色に近い深い赤で、5段階ある色の評価で「5」をつけられた珊瑚は、大変価値が高く高価買取が期待できます。 赤味が薄く、色ムラが発生しているものは価値が下がってしまいます。 カラー 珊瑚の買取市場で最も高値で取引されやすいのが、血赤珊瑚と呼ばれる赤黒い色合いが特徴の珊瑚です。 血液に近い深い赤色であるほど重量感があり、宝石として加工した際に奥深さが感じられるとして、高い価値がつきます。 血赤珊瑚のカラーまでいかずとも、美しい赤色の紅珊瑚は、高額買取されやすいといえます。 色合いが濃く、きれいな赤色の発色をしている珊瑚は、高額査定が期待できるでしょう。 珊瑚といえば、赤色やピンクを想像する人も多いと思いますが、実は白珊瑚も人気があります。 白と一口にいっても、純白や乳白色など、色味に若干の違いがあり、珊瑚自体が貴重になっている現在では、白珊瑚も高値で取引される傾向です。 フラクチャー フラクチャーとは、傷やひび割れ、虫食いなど自然にできたダメージを指します。 珊瑚の傷やひび割れは「ヒ」と呼ばれ、この「ヒ」や虫食いが少ないほど、査定額がアップします。 また、一部の珊瑚には「フ」と呼ばれる白い筋が内部にあり、宝石として加工された際にこの「フ」が表面に出てきてしまうと、査定額にマイナスの影響を与えてしまうでしょう。 珊瑚の買取は実績ある買取業者へ相談を 珊瑚の買取を検討している方は、実績豊富な買取業者へ相談しましょう。 珊瑚の価値は、専門知識と技術がなければ正しく判断するのが難しいといえます。 そのため、専門家のいない業者を利用してしまうと、適切な価値をつけてもらえないかもしれません。 珊瑚の買取実績のある骨董品買取業者であれば、珊瑚の価値に見合った適切な価格を提示してもらえるでしょう。
2024.12.01
- すべての記事
- 骨董品
- 骨董品買取
- 骨董品全般
-
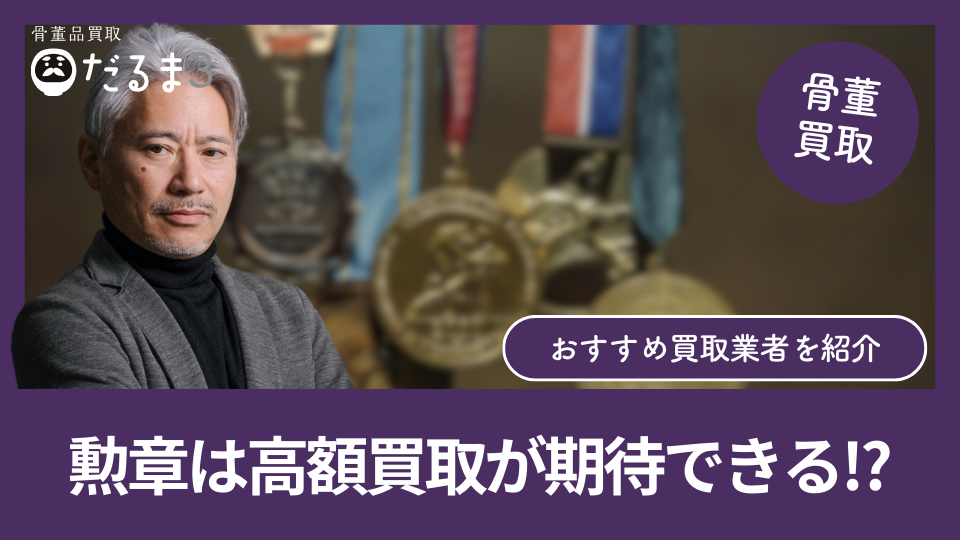
勲章は買取してもらえる?高額査定のポイントとは
明治時代に創設され、国や公共のために尽力を尽くした人や、社会分野で優れた功績を残した人に贈られる勲章。 国が与える名誉の標章で、現在も運用されています。 勲章は、特定の人しか受け取れないもののため、希少価値が高くコレクターが多くいます。 勲章の買取依頼を検討中ですか? 「親族の遺品整理で勲章を譲り受けた」、「勲章はどこで買い取ってもらえるのだろう」など、勲章を手放す方法に悩んでいる方は多いのではないでしょうか。 勲章の処分方法にお困りの方は、専門業者による買取を検討しましょう。 勲章は、誰でも手に入れられるものではなく、貴重なものであるため、そのまま捨ててしまうのはもったいありません。 勲章を収集する熱心なコレクターもいるため、買取査定に出して売却するのがお勧めです。 いつの時代も勲章は人気 勲章は、特定の人物を讃えるために与えられるもののため、一般の人が簡単に手に入れられるものではありません。 その希少価値の高さから、一部のコレクターから人気の高いものでもあるのです。 数が少なく限定感がある点や、見た目の美しさから収集しているコレクターも多く、人気を集めています。 自宅に眠る勲章はありませんか もらった勲章を本人が手放すことはあまりありませんが、親族や家族から相続された際、扱いに悩む人も多いのではないでしょうか。 勲章は、もらった本人以外が着用するのを禁止されています。 また、祖父母や親族から譲り受けても、自分が功績を挙げたわけではないため、その栄誉を得られるわけでもありません。 そのため、手放したいと考える人も多いでしょう。 もし、譲り受けた勲章の扱いに困っているのであれば、専門の買取業者に相談してみませんか。 勲章の買取実績のある業者であれば、勲章の価値を正しく判定して適切な価格で買い取ってくれるでしょう。 勲章を高額買取してもらうには 勲章の買取価格は、状態や付属品の有無、セットになる軍服や軍装品の有無などによっても変動します。 どのようなものが高価買取されやすいのかを知り、所有している勲章に該当する条件があるかを確認してみましょう。 傷や変色などのダメージがないか 勲章に限らず、骨董品全般にあてはまることですが、傷や変色、欠けなどがない新品に近い状態のものほど高く買取してもらえる傾向です。 勲章は、七宝製が多く釉薬が剥げてしまったり、突起部分が折れてしまったりする可能性があります。 また、綬という勲章用のリボンは汚れやすいため、適切に保管する必要があります。 むき出しのまま置いておくと、汚れや傷がつきやすくなるため、ケースに入れて保管しておくのがお勧めです。 買取査定を依頼する際は、お手持ちの勲章の状態を事前にチェックしておきましょう。 付属品はそろっているか 勲章には、箱や勲記などいくつかの付属品がついています。 勲章の保存用の箱は、漆で塗られた専用のケースが用意されており、勲章の種類と勲等が箱に書かれています。 箱があるかないかで、査定額が大きく変わるため、勲章を受け取った際は箱があるか必ず確認しましょう。 また、勲記とは勲章の証明書のことで、勲章と勲記はセットで授与されるケースがほとんどです。 そのため、セットで査定に出すと買取額がプラスになる可能性が高いでしょう。 勲記は紙で作られており劣化しやすいため、シミや破れなどに十分注意し、勲章とセットで保管しておくことをお勧めします。 あわせて軍服や軍装品がないか 勲章を買取査定に出す際、軍服や軍装品なども所有していれば、あわせて査定に出しましょう。 勲章は、勲等や保存状態によっては1点のみでの買取ができない可能性があります。 その際に、旧日本軍の軍服や軍装品、軍刀などがあれば、あわせて買取査定してもらえる場合があります。 遺品整理や相続では、勲章や軍服、軍装品をセットで譲り受けるケースも多いようです。 もし関連するものをセットで受け取ったら、すべてまとめて保管しておくことをお勧めします。 勲章を手放すとき、どんな方法がある? 勲章を手放す方法としては、ネットオークションやフリーマーケット、リサイクルショップ、不用品回収業者や遺品整理業者、骨董品買取業者などがあります。 それぞれ特徴が異なるため、自分と手放したいアイテムにあった方法を選ぶことが大切です。 ネットオークションやフリーマーケットは、自由に価格を決められるメリットがあります。 勲章の価値を知っていれば、希望価格やそれ以上の価格で売却が可能です。 しかし、正しい価値を知らなければ相場よりも低い価格で販売してしまい、損をしてしまう可能性があります。 また、すぐに買い手がみつかるとは限らず、時間が経てば値下げ交渉が行われる場合もあるでしょう。 リサイクルショップでの売却は、早くて当日中に換金できるメリットがあります。 急いで手放したいと考えている方に向いている方法といえますが、買取価格が相場より低くなる傾向です。 勲章に関する専門知識をもつスタッフが在籍しているとは限らないため、適切な価値を判断できない可能性が高いでしょう。 不用品回収業者や遺品整理業者は、ほかの遺品や相続品もまとめて回収してもらえるメリットがありますが、リサイクルショップ同様に専門家がいる可能性は低いため、買取価格が安くなってしまう可能性があります。 また、まとめて買取となるため一つひとつの価格がわからないのもデメリットの一つといえます。 骨董品買取業者であれば、勲章の買取実績があったり、勲章に詳しい査定士が在籍していたりする可能性が高いでしょう。 高価買取を狙うのであれば、価値を正しく判断できる専門業者への査定依頼がお勧めです。 ただし、業者によって実績はバラバラなため、勲章の買取実績が豊富な業者を選ぶとよいでしょう。 査定を無料で実施している業者も多いため、複数の業者に依頼して相場を確認することも大切です。 高価買取が狙える勲章の種類 勲章の中には、旧日本軍時代に功績が評価され授与されたものもあるでしょう。 勲章の中でも、そのような明治時代や大正時代、昭和時代に授与された勲章には、希少価値や歴史的価値の高いものも多くあります。 旭日章 旭日章は、1875年に制定された日本で初めての勲章です。 日章を中心に、光線を配し、鈕には桐の花葉が用いられているデザインが特徴的です。 社会のさまざまな分野の功績に着目し、優れた功績を挙げた人を表彰する際に授与される勲章として用いられました。 勲一等から勲八等までの8等級に分けられており、ほかの勲章よりも上位に位置するといわれています。 瑞宝章 瑞宝章は、1888年に制定された勲章で、社会や公共のために功労がある人物を讃えるために授けられる勲章です。 男女共通して、国または地方公共団体の公務や公共的な業務に長年従事して、功労を積み重ねた人を表彰するために授与されます。 古代の宝である宝鏡を中心に、大小16個の連珠、四条や八条の光線を配し、桐の花葉が用いられたデザインです。 制定時は8等級ありましたが、2003年の改正により現行の6等級に変更されています。 宝冠章 宝冠章は、1888年に制定され、女性に限定した唯一の勲章です。 科学技術や芸術といった文化の分野で優れた功績を挙げた人に授与されるもので、天皇の名をもって皇后から授与される勲章です。 2003年の改正により、それまで男性にのみ授与されていた旭日章・桐花章・菊花章が、女性にも授与されるようになったため、現在宝冠章は、女性皇族や外国人に向けた儀礼的な運用にのみ使用されています。 金鵄勲章 金鵄勲章は、陸海軍人や軍属に授与される終身年金付きのもので、日本で唯一の武人勲章です。 日清戦争から日露戦争、第一次世界大戦、満州事変、志那事変、太平洋戦争までの間に、約83万人の軍人に授与されましたが、戦後、1947年に勲章自体が廃止されました。 金鵄勲章は、神武天皇東征時に天皇の弓にとまった金鵄がデザインされており、綬はエメラルドグリーンで白い線が左右に一本ずつ入った構成になっています。 景雲章 景雲章は、旧満州国で授与されていたもので、13年半しか運用されなかったため数の少ない勲章です。 日本の旭日章に相当する勲章で、勲一位から勲八位まで8等級ありました。 白地に赤線が左右に一本ずつ入る綬で、綬の下には満州国皇室の紋章である蘭花紋を意匠化したデザインが施されています。 記章 記章は、日本政府や日本赤十字社などの主宰者から従軍や寄付などの功労が認められた人に渡されるバッジやメダルを指します。 勲章とは異なり、栄誉や功績を讃えて授与されるものではなく、発行枚数も多いものですが、種類が大変多いことから、コレクター人気の高いアイテムです。 勲章の買取は実績ある買取業者へ相談を 親族や祖父母の遺品整理で受け取った勲章の扱いに悩んでいる方は、買取実績豊富な専門業者に査定の相談をするのも一つの手段です。 価値の高い勲章は、レプリカも多く流通しているため、適切に判断してもらうためにも、知識のある専門家に確認してもらう必要があります。 歴史的な意味合いもあり、コレクションとしての需要も高い勲章は、高価買取が狙えるアイテムの一つです。 自宅で保管していた勲章を手放すなら、勲章に詳しい査定士が在籍する買取業者に相談しましょう。
2024.12.01
- すべての記事
- 骨董品
- 骨董品買取
- 骨董品全般
-

翡翠を高額買取してもらおう
深い緑色と美しい光沢が魅力的な翡翠は、上品で奥ゆかしさが感じられる宝石として人気を集めています。 翡翠は、古くから「玉」と呼ばれ、金以上の価値がある宝石として親しまれてきた歴史もあります。 美しく価値の高い翡翠を手放す際は、価値の分かる買取業者に相談することが大切です。 翡翠の買取依頼を検討中ですか? 遺産相続で譲り受けた翡翠のアクセサリーや置物の処分にお困りの方もいるでしょう。 なかなか自分では利用する機会がない、置き場所がない、などの理由で翡翠を手放したいと考える方もいます。 翡翠は、価値ある宝石のため、捨てるのではなく買取依頼に出すのがお勧めです。 適切な価格で売却して、必要とする人のもとに渡れば、大切な翡翠はさらに美しさを増していくでしょう。 いつの時代も翡翠は人気 翡翠は、身につければ身につけるほど美しさが増す宝石で、「色が育つ宝石」とも呼ばれています。 翡翠は、肌の油分によってツヤが増していく特徴をもっているため、そのように呼ばれているのです。 多くの宝石は、汗や皮脂に弱いため、油分が表面についてしまうと美しい外観が損なわれてしまいますが、翡翠は乾燥に弱く適度な油分が必要なため、身につけたり触れたりするほどツヤと透明感が増していきます。 使うほどに美しさが増していく翡翠は、古くから親しまれてきている宝石です。 自宅に眠る翡翠はありませんか コレクションしていた宝石の一つとしてや、相続品の一つとして翡翠を所有している人もいるでしょう。 自宅に眠る翡翠を手放すなら、買取業者への相談をお勧めします。 翡翠は、宝石の一種であるため、本物であれば高い価値がつくかもしれません。 自分では使わないが、捨てるのはもったいないと感じている翡翠があれば、専門知識をもつ買取業者へ査定を依頼しましょう。 高価買取が狙える翡翠かチェックするポイントは? 翡翠は宝石の一種で、クオリティの高いものであれば高価買取も期待できる製品です。 翡翠の価格を決めるポイントには、カラット・カラー・透明度・加工方法などがあります。 それぞれの項目でどのような特徴をもつ翡翠が高価買取されやすいのか知っておくと、査定依頼に出した際、価格を把握しやすいでしょう。 カラット 翡翠は、カラット数が大きいほど希少価値が高まり、高価買取が期待できます。 特に、翡翠の最高峰といわれている琅玕は、カラット数の違いにより査定額が大きく変動します。 同じ品質の琅玕であっても、カラット数が異なるだけで、数十万~数百万単位の価格差が発生するようです。 ただし、翡翠の中でもネフライトは、原則カラット数が大きくなっても、査定価格が大幅に上昇することはありません。 カラー 翡翠といえば、緑色のイメージが強い人も多いのではないでしょうか。 しかし、翡翠には白や黒、赤、ラベンダーなどさまざまなカラーのものが存在します。 同じ品質の翡翠でも、カラーの違いによって査定価格が大きく異なる場合があります。 定番カラーはやはり緑色で、流行り廃りがないため価値がつきやすいカラーです。 近年は、上品で優しい色合いのラベンダーや、中国で定番カラーになっている白などの人気も高まっています。 それ以外のカラーの翡翠は、品質がよくても人気カラーに比べると高額査定がされにくい傾向です。 また色の種類だけではなく、色ムラも翡翠の価値を大きく左右します。 色ムラが少なく、均一な色合いであるほど高価買取が期待できます。 透明度 翡翠の価格は、透明度にも影響を受け、透明度が高いほど価格も高くなるでしょう。 質の高い翡翠の中には、石を通して新聞の文字が読めるほど透明感があるといわれています。 一般的に、翡翠は色が濃いほど透明度が低くなるため、色が濃くて透明度の高い翡翠は大変希少性が高く、高価買取が期待できるでしょう。 ただし、透明度が高い翡翠の中には、樹脂で固めた人工の製品もあるため、査定時にあまり価値がつかない可能性もあります。 加工方法 翡翠は、加工方法の違いによっても価値が大きく変わります。 天然の翡翠は、表面がザラザラしているため、光沢感を出すために研磨したりワックスを塗ったりして、表面を滑らかに整える必要があります。 加工方法は主に、A貨・B貨・C貨の3つに分けられ、どの基準によって加工された翡翠であるかが買取価格に大きく影響を与えるのです。 最もランクの高いA貨は、表面のザラザラを研磨し、無色のワックスでツヤ出ししたもので、この加工処理により翡翠の価値が下がることはほとんどなく、天然に近い状態の製品として高価買取が期待できます。 B貨は、透明感を出すために漂白処理を施し、美しい色合いを発色させるために樹脂を染み込ませる加工などを行います。 これらの加工を施された翡翠はB貨に分類され、A貨よりも価値が下がってしまうでしょう。 C貨は、翡翠の粉末を練り固めて成形したり、質の低い翡翠に塗料をコーティングしたりした人工の翡翠であり、宝石としての価値はほとんどないといわれています。 翡翠を手放すとき、どんな方法がある? ネットオークションやフリーマーケット、リサイクルショップ、不用品回収業者や遺品整理業者、骨董品買取業者など、翡翠を手放す方法はいくつもあります。 ネットオークションやフリーマーケットは、自分で金額を設定できるため、希望する価格で売却できるメリットがありますが、自分が翡翠の価値を正しく理解していないと、低い価格設定で損をしてしまう可能性があるでしょう。 また、お客さんと直接やり取りする必要があるため、慣れていないとトラブルに巻き込まれてしまう可能性もゼロではありません。 リサイクルショップは売りに行ったその日に換金できるメリットがありますが、貴石を専門に扱うお店ではないため、適切な価格をつけてもらえない場合があります。 不用品回収業者や遺品整理業者に依頼すれば、翡翠だけではなく手放したい品物をまとめて引き取ってもらえるメリットがありますが、こちらも買取価格が低くなってしまう可能性が高いでしょう。 価値ある翡翠を正しい価格で手放したいと考えている方は、経験豊富な骨董品買取業者への依頼がお勧めです。 無料で査定してくれる業者も多いため、まずは相談してお手持ちの翡翠の価値を知るのもよいでしょう。 高価買取が期待できる翡翠の種類は? 翡翠は、2種類の鉱物の総称であり、ジェダイトとネフライトがあります。 どちらの種類であるかによって、買取価格は大きく変動するため、お手持ちの翡翠の買取を検討している方は、どちらの翡翠に該当するかおおよそ判断できるようにしておくとよいでしょう。 ジェダイト(硬玉) ジェダイトは、本翡翠と呼ばれる鉱石で、ダイヤモンドやサファイアなどと同じ貴石の仲間として、宝石としての価値をもっています。 ジュエリーとして扱われている翡翠は、ジェダイトのことを指しています。 ジェダイトは、宝石の硬さを表すモース硬度が、6.5から7とネフライトよりも硬いことから、硬玉と呼ばれることも。 純粋なジェダイトは、白色ですが、鉱物を構成する成分により石の色が変化するため、カラーが豊富な特徴もあります。 クロムと鉄を含むと緑色、鉄やマンガンを含むと紫色になる性質をもっています。 ネフライト(軟玉) ネフライトは、主に中国で採取されるもので「中国翡翠」とも呼ばれています。 ネフライトのモース硬度は、6から6.5とジェダイトよりも柔らかいことから、軟玉と呼ばれることも。 ネフライトは、貴石ではなく半貴石の仲間になるため、宝石としての価値をもっていません。 しかし例外もあり、新疆ウイグル自治区の一部で採取されている「和田玉」の中で、白くて柔らかな色合いをもつものは「羊脂玉」と呼ばれ、高価買取が期待できます。 翡翠の見分け方 翡翠とひと口にいっても、ジェダイトとネフライトでは、価値が大きく異なります。 買取査定に出す前に、所有している翡翠がどちらの種類であるか事前に把握したいと考える人も多いでしょう。 翡翠の種類を判別するためには、翡翠の透明感や色の均一さを確認する必要があります。 光をあててみる 翡翠が本物であるか見分ける方法として、光をあててみることが挙げられます。 透明度の高い翡翠であっても、天然に採取されたものには必ず内包物や濃淡がみられます。 しかし、気泡が入っていたり、中に何も入っておらず完全な透明であったりする場合、ほかの鉱物やガラスの可能性があるでしょう。 色が均一であるか 翡翠は、色ムラが少ないほど価値が高まりますが、ムラが一切ない翡翠はありません。 翡翠の表面をよく観察してみて、色ムラがありつつも色彩に均一性があるものは、本物の翡翠である可能性が高いでしょう。 一方、まったく色ムラがみられなかったり、ムラが不規則な色合いをしていたりするものは、人工の偽物やほかの鉱物の可能性があります。 翡翠の買取は実績ある買取業者へ相談を 翡翠の買取を検討している方は、買取実績が豊富な業者への相談がお勧めです。 宝石の仲間である翡翠は、本物であれば高価買取が狙える製品であるため、価値を正しく判断してくれる業者に依頼する必要があります。 骨董品買取業者の中でも、貴石や宝石などの査定実績が多い業者であれば、適切な価値をつけてくれる可能性が高いといえるでしょう。 自分では使わなくなった翡翠をお持ちの方は、捨ててしまったり、ほかのものとまとめて回収してもらったりするのではなく、専門業者に査定を依頼するのがお勧めです。
2024.12.01
- すべての記事
- 骨董品
- 骨董品買取
- 石(銘石・鑑賞石)
-

骨董品価値あるビスクドールを高額買取してもらおう
焼き重ねられて作られた顔と、濡れたようにきらきらと光るガラスの瞳が特徴のビスクドール。 写実的で精巧な作りが魅力のビスクドールの中には、希少価値が高く、高価買取が期待できる人形もあります。 ビスクドールを処分する際は、捨ててしまわずに、買取査定に出すのがお勧めです。 ビスクドールの買取依頼を検討中ですか? ビスクドールは、西洋骨董品の中でも人気の高いジャンルの一つで、世界中に熱心なコレクターが存在します。 そのため、ものによっては需要が高く、買取でも高値がつきやすいのです。 ビスクドールの中でも、1930年以前の古い時代に作られたアンティークものを中心に高値で取引が行われています。 いつの時代もビスクドールは人気 ビスクドールをよく見てみると、豊かなブロンドヘアに長いまつ毛、クリっと輝く目など大変精巧に作られています。 きれいな人形ですが、少し怖いと感じる方もいるのではないでしょうか。 そんなビスクドールをコレクションする収集家は、現在も世界中にたくさんいます。 そのため、珍しいビスクドールや状態のよいビスクドールなどは高値での買取が期待できるでしょう。 自宅に眠るビスクドールはありませんか 自宅にしまったままのビスクドールをお持ちの方はいませんか。 ビスクドールは、適切な方法で保管していないと経年劣化とともに傷んでいってしまいます。 状態が悪くなってしまえば、買取が困難になってしまう可能性もあるため、しまったままで利用する予定のないビスクドールは、思い切って買取に出してしまうのも一つの手段です。 買取に出せば、手元にお金が入ってくるとともに、ビスクドールを必要としているコレクターのもとに人形が渡り、大切にしてもらえます。 自分のためにも、ビスクドールのためにも、自宅で眠っている人形があれば、まずは買取査定に出してみましょう。 ビスクドールを高額買取してもらうには 価値のわからないビスクドールを手放すとき、なるべく高値で買い取ってもらえたらうれしいと考えるでしょう。 ビスクドールの価値が何で決まっているのかを確認しておくと、買取価格のおおよその目安がわかるようになります。 本物であることはもちろん、作られた工房や人形の品質、付属品の有無、人形のサイズなどが価格に大きくかかわってきます。 どの工房で作られているか ビスクドールには、どの工房で作られた人形であるかわかるように、刻印が施されています。 工房ごとの刻印は、一般的に人形の髪の毛を上げた後頭部の場所や、項の部分にあります。 刻印からは、工房名や制作国、サイズ、およその制作年代が判別できるようになっているのです。 工房ごとの評価は、一般的にドイツよりもフランスの工房のほうが高くなり、さらに同じ工房でも制作年代によって評価が変わることもあります。 ドール本体や衣装の品質 ビスクドールの価値は、工房のブランド力の影響も大きいですが、同時に人形や衣装の品質も買取価格に大きな影響を与えます。 ビスクドールの魅力は、フェイス・ボディ・衣装にあります。 ビスクドールの頭部は、磁器でできており、磁器土を流し込む石膏の型によって人形の表情が大きく変化するのです。 表情が精密かつ豊かに表現されているかなどの出来栄えが査定でもポイントになります。 また、ビスクドールの瞳は、ペーパーウェイトアイ、ブロウアイ、スリープアイなどの技法を駆使して制作されており、中でもペーパーウェイトアイは最高峰の技法といわれており、この技法の違いも査定額に影響を与えると考えられるでしょう。 ビスクドールの価値は、本体の品質だけではなく衣装にも影響を受けます。 ビスクドールが作られた当時の衣装を身につけているか、素材がアンティークであるか、近年新しく作られたものであるかなどの違いによって価格が変動します。 付属品がそろっているか ビスクドールを買取査定に出す際は、人形本体以外に着替えの衣装や、トランク、人形用の机やいすなどの付属品も査定対象となります。 付属品がそろっているほど買取額が高くなる傾向のため、ビスクドールを所有している人は付属品をどのくらいもっているか確認しておきましょう。 また、証明書や保証書は、ビスクドールが本物であるか判断する大切な資料になるため、捨てずに人形とともに保管しておいてください。 サイズはどのくらいか ビスクドールは、一般的にサイズが大きいほど高い価値がつきます。 同じ工房で作られたビスクドールでも、サイズが大きいものほど評価は高くなると考えられます。 ビスクドールを手放すとき、どんな方法がある? ビスクドールを手放すと決めても、どのような方法があるかわからない方もいるでしょう。 買取や売却の方法を把握し、自分に合った方法でビスクドールを手放せるようにすることが大切です。 ネットオークションやフリーマーケットで売却 ビスクドールは、ネットオークションやフリーマーケットでも売却が可能です。 オークションを利用すれば、自分で自由に価格を設定できるとともに、希望価格以上で取引できることもあるでしょう。 ただし、ネットオークションやフリーマーケットは、すぐに買い手がつかないこともあります。 値引き交渉をされ、最初の希望価格よりも低い値段で販売しなければならないことも。 また、所有しているビスクドールの価値を自分で正しくわかっていないと、大きく損をしてしまう可能性もあるため注意が必要です。 リサイクルショップで売却 ビスクドールは、リサイクルショップでも売却できます。 リサイクルショップの店舗に手放したいビスクドールを持ち込めば、最短即日で売却が可能です。 今すぐビスクドールを売って、手元に現金が欲しいという方には、向いている取引といえます。 ただし、リサイクルショップの店員が、必ずビスクドールの価値に詳しいわけではありません。 そのため、本来の価値よりも低い価格で買取されてしまう可能性があるでしょう。 ネットオークションやフリーマーケットと同様に、自分がビスクドールの価値をわかっていないと安く手放してしまうおそれがあります。 不用品回収業者や遺品整理業者へ相談 不用品回収業者や遺品整理業者でも、ビスクドールを引き取ってもらえる場合があります。 ビスクドール以外にも買取してもらいたいものが多くあり、まとめて引き取ってもらいたいときに便利な方法です。 回収とともに片付けも行ってくれるため、自宅を整理したいときにお勧めです。 ただし、まとめて回収されるため、一つひとつの価格がわかりにくいデメリットがあります。 また、ビスクドールに詳しいスタッフがいるとは限らないため、適切な価格をつけてもらえない可能性があるでしょう。 高価買取が期待できるビスクドールブランドは? ビスクドールの価格には、どのブランドで販売されていたものかが大きく影響します。 そのため、ビスクドールの買取を検討している方は、高値で取引されやすい人気ブランドを把握しておくとよいでしょう。 ジュモー ジュモーは、19世紀半ばごろにフランス・パリの郊外に設立されたブランドで、フランスを代表する工房の一つです。 ビスクドールが全盛期の時代に、製造・販売をけん引したブランドの一つといえます。 憂いを含んだ表情とファッション性の高い衣装が人気で、現在でも高値でやり取りされている人形が多いブランドです。 ゴーチェ ゴーチェも、19世紀半ばごろのフランスのブランドで、頭部の製造技術の高さが特徴です。 その高い技術は特許も取得しており、ジュモーをはじめとしたほかのブランドから依頼されて頭部を納品していたともいわれています。 繊細な作り込みで人気を集め、現在の買取市場でも活発に取引が行われています。 ブリュ ブリュも、19世紀半ばごろにフランス・パリの郊外に設立されたブランドで、高い技術力を備え、繊細かつ精巧な仕上がりのビスクドールは、当時から多くのファンの支持を集めていました。 フランス最大級のビスクドール工房の一つで、現在でもこの工房で製造された人形は、アンティーク品として高い価値を保っています。 アーテ アーテは、アンドレ・ジャン・トュイエという作家が制作したビスクドールです。 現存する資料が少なく、1875年から1890年に、トュイエの名の作家がいたことしか記録に残っておらず、現存するビスクドールも少なく希少価値の高い人形です。 ビスクドールの買取は実績ある買取業者へ相談を 繊細な表情や精巧な作りが魅力のビスクドールを手放すなら、買取実績が豊富な専門業者への依頼がお勧めです。 ビスクドールの価格は、専門的な知識がなければ正しく判断できないでしょう。 自分もしくは家族が大切にしていたビスクドールを手放すなら、適切な価格で売却したいものです。 そのため、骨董品買取業者を選ぶ際も、ビスクドールの買取実績をチェックするようにしましょう。
2024.12.01
- すべての記事
- 骨董品買取
- 西洋美術・西洋アンティーク
-
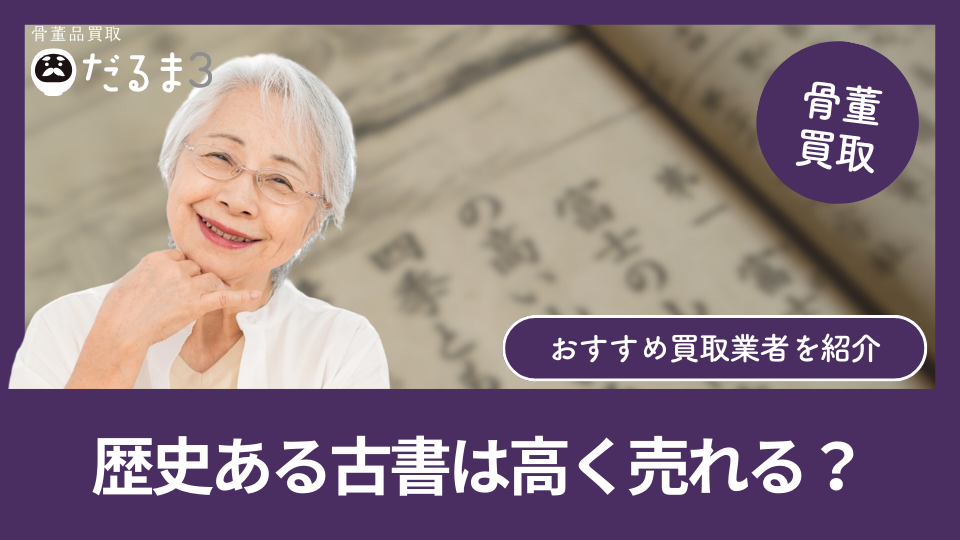
古書は歴史的価値が高い?骨董品として高額買取してもらうポイント
古い本や使わなくなった本を自宅にしまったままの人も多いでしょう。 自宅に眠っている本の中には、ただの古本と思っていても、実は歴史的価値のある古書があるかもしれません。 そのまま処分してしまうのではなく、一度査定に出して価値を知ってみるのもよいでしょう。 古書の買取依頼を検討中ですか? 遺品整理やコレクション整理で、利用しなくなった古書の買取を検討中の方もいるでしょう。 古書とひと口にいっても、歴史書や哲学書、思想書、仏教書、美術書、映画雑誌など、そのジャンルは多岐にわたります。 自分では、古書の価値を判断するのは難しいため、専門知識のある業者に依頼して査定してもらうのがお勧めです。 いつの時代も古書は人気 古書は、自分が若いころに読んでいた本や、幼いころに親が読んでいた本など、懐かしい本に出会える魅力があります。 また、すでに絶版になっており、新品を購入できない本でも、古書でなら手に入れられる可能性があるでしょう。 古い時代に書かれた貴重な古書は、歴史的価値があるものとして買取価格がアップすることも。 手に入りにくい古書は、コレクターの間でも人気が高いため、需要があり買取してもらいやすいといえます。 自宅に眠る古書はありませんか 長年、研究や専門として学んできた書物や、亡くなった家族が大切にしていた古書など、使わないけど捨ててしまうのは寂しいと、自宅に保管し続けている本はありませんか。 処分に困っている古書をお持ちの場合は、一度専門の買取業者に査定を依頼するのがお勧めです。 古書の正しい価値を教えてくれるとともに、販売を通してほかに必要としている人の手元に届けてもらえる可能性があります。 大切にしていた本を捨ててしまうのではなく、必要としている人に読んでもらえるのであれば、手放すのも寂しくないでしょう。 古書を高額買取してもらうには 古書は、ジャンルや種類によってその価値が大きく変動するものです。 大切な古書を納得いく価格で手放すためにも、買取を依頼する際は、どのような種類や状態の本が高値で買い取ってもらいやすいかを、事前に把握しておきましょう。 人気や話題のある作品か 人気作や話題になっている本は、通常よりも価格が高くなるケースもあります。 人気や話題のある本は、市場価値や需要が高く、売れやすいため買取価格もアップすると予想されます。 たとえば、ノーベル文学賞や芥川賞などの賞を受賞した作家の本であれば、話題性が高まっているタイミングの方が買取価格が高くなるでしょう。 また、ドラマ化やアニメ化、映画化などされると、一度人気が落ち着いていた本でも再び話題性が高まり、高値で買い取ってもらえる可能性があります。 保存状態がよいか 本の保存状態は、買取価格に大きな影響を与えます。 傷や汚れ、日焼けなどのない新品に近い本であるほど、買取価格は高くなるでしょう。 そのため、古書を保管しておくときは、日の当たらない風通しのよい場所など、適切な環境で保管することが大切です。 ただし、汚れや傷みがあるからといって、まったく買取価格がつかないわけではありません。 もともと製作された年代が古く歴史的価値のある古書は、多少の汚れや傷みがあっても、高価買取が期待できます。 保存状態がよくないからと処分せず、まずは査定に出してみるのがお勧めです。 帯がついているか 本に帯がついたままであると、買取価格がアップする可能性があります。 特に、コレクションとして価値のある本であれば、帯に特別な情報が記載されており、単体では手に入りにくいため、本と帯がセットになった状態で買取に出せば買取価格がプラスになると期待できるでしょう。 そのため、購入した本に帯がついている場合は、捨てずに取っておくことをお勧めします。 帯を本につけっぱなしにしておくと、落ちてどこかにいったり、破れてしまったりするおそれもあります。 心配な方は、別で保管しておくとよいでしょう。 古書を手放すとき、どんな方法がある? 古書を手放す方法は、さまざまあり、各方法によってメリット・デメリットが存在します。 それぞれの方法や特徴を知り、自分が所有する古書を手放す際に、どの方法を利用すればよいか判断できるようにしましょう。 ネットオークションやフリーマーケットで売却 古書を手放す方法として、ネットオークションやフリーマーケットを利用して、自分で売却する方法があります。 価格を自分で設定できるため、納得のいく価格で売却ができるでしょう。 ただし、古書の価値を正しく把握していないと、本来よりも低い価格設定をしてしまい、損をしてしまう可能性があります。 また、値下げ交渉をされる場合もあり、希望する価格で売却できないケースもあるでしょう。 ネットオークションやフリーマーケットを利用するのであれば、正しい価値を把握し、希望価格以上で売却できる工夫をする必要があります。 リサイクルショップで売却 古書は、リサイクルショップでの売却も可能です。 リサイクルショップは、店頭に持ち込んで早ければ即日売却可能な点がメリットといえます。 今すぐ処分して、手元に現金を残したいと考えている人には、お勧めの方法です。 しかし、すべての古書が買い取ってもらえるわけではなく、中には価格がつかないものもあるかもしれません。 リサイクルショップに、必ず古書を専門とするスタッフがいるわけではないため、歴史的価値がある古書でも、価値を判断できず低く見積もったり、価格がつかないと判断されてしまったりする場合があるのです。 古書の価格を適切に判断してもらいたい人は、別の方法での処分を検討しましょう。 不用品回収業者や遺品整理業者へ相談 不用品買取業者や遺品整理業者は、古書に限らず多種多様な不用品・遺品をまとめて回収してくれるメリットがあります。 処分するものの数が多い場合や大きいものが多い場合には、持ち出す必要がないため便利な方法です。 ただし、リサイクルショップでの売却同様に、対応してくれるスタッフが古書に対する専門知識を備えているとは限りません。 本来の価値に気づけず低い価格での売却になってしまったり、回収したものをまとめて価格を提示されてしまったりすることもあるでしょう。 大切にしてきた古書を適切な価格で手放したい方は、専門知識のある業者に依頼するのがお勧めです。 骨董品買取業者へ相談 古書の処分方法で迷っている方は、骨董品買取業者への依頼を検討しましょう。 専門業者であれば古書に関する知識を持ったスタッフがおり、価値に見合った買取価格をつけてもらえる可能性が高いといえます。 ただし、骨董品買取業者であっても依頼先によって買取実績が異なることもあります。 さまざまなジャンルの骨董品を取り扱っている業者も多いため、古書の買取実績が豊富な依頼先を見つける必要があるでしょう。 骨董品買取業者は、無料査定を実施しているケースも多いため、まずは複数の業者に査定を依頼して、価格の相場を確認するのもお勧めです。 古書本来の価値を適切に判断してもらいたい方は、実績が豊富な骨董品買取業者に依頼しましょう。 高価買取が期待できる古書は? 古書とひと口にいっても、さまざまなジャンルがあるため、買取を検討している場合は、どのような種類の古書が高価買取されやすいのか知っておく必要があります。 歴史的価値のある書物 古文書や和本などは、歴史的価値が高いとして、高価買取されやすい傾向です。 たとえば、江戸時代の古文書や中国が宋・明の時代の書物は、歴史資料として大変貴重であると考えられます。 また、このような古い時代の医学書や書画なども高価買取が期待できます。 学術的要素の強い書物 哲学や思想、宗教などの人文科学系の学術的要素の強い本は、高価買取が期待できます。 さらに、全集そろっているか、月報がついているかなどによっても買取価格は変動します。 専門性の高い仕事をしていた人がご先祖様にいる場合は、遺品整理の際にチェックしてみるとよいでしょう。 戦前の挿絵入り書物・絵葉書・写真 戦前の挿絵入り書物は、本の内容ではなく挿絵の存在によって買取価格がアップする場合があります。 また、戦前に作られた絵葉書や写真、満州関連の資料文献なども、歴史的資料となる可能性が高く、高価買取が狙える古書です。 1970年代以前の鉄道や自動車に関する書物 鉄道や自動車に関連した書物の中でも、特に1970年代より前に作られた本は、高値がつけられる可能性があります。 1970年代以前の自動車は、現在でも人気の高い名車が多いため、古書に関しても買取価格がアップすると予想されます。 また、鉄道は時代の移り変わりによって消えていき、新しいものが生まれていっているため、鉄道が好きな人にとっては、昔の鉄道が掲載された古書は、大切な資料になるといえるでしょう。 古書の買取は実績ある買取業者へ相談を 自宅に眠っていた古書を処分するのであれば、まずは実績のある買取業者に相談しましょう。 さまざまなジャンルがあり、種類や状態によって価値が変動する古書の価値を自分で判断するのは難しいといえます。 適切な価格で手放すのであれば、複数の業者へ査定を依頼し、価値を把握することが大切です。 骨董品買取業者の中でも、特に古書の買取実績が豊富な業者であれば、お手持ちの本の価値を適切に判断してくれるでしょう。
2024.12.01
- すべての記事
- 骨董品買取
- 骨董品全般
-

仏像を高額買取してもらうには?高く売るコツとポイント
仏像は、仏教徒でなくても彫刻の美しさや仏像それぞれの表情など、眺めているだけで心が洗われるような気持ちになれます。 自分の心の在り方を見つめ直したり、気持ちを整えたりするために、先代が仏像を持っていたという家もあるのではないでしょうか。 仏像は骨董品として価値があり、仏像が好きな人はもちろん、骨董品のコレクターからも人気です。 仏像を買取してもらうには、どのような業者がよいのか、どの仏像作家の作品が骨董価値が高いのかなど仏像の買取について見ていきましょう。 仏像の買取依頼を検討中ですか? 仏像が家にあっても神聖なもののイメージがあり、手放すとなると簡単に捨てられず、どうすればよいか迷ってしまうこともあるでしょう。 せっかくなら、仏像に魅力を感じている人に譲りたいものです。 実は、仏像は状態や作家によって、骨董品として高額買取してもらえる可能性があります。 いつの時代も仏像は人気 昔は、仏教の信仰が篤かった時代もあり、仏像を所有する家もたくさんありました。 現代は宗教も多様化し、仏像もインテリアとして楽しむ人や、仏教を信仰していなくても仏像の魅力を楽しむ人がいます。 現代にも人気の仏像作家は存在し、仏像の魅力を伝え続けています。 日本に古くからある仏像は、こうして昔も今もたくさんの人に愛されているのです。 自宅に眠る仏像はありませんか 昔から代々受け継がれてきたものや、最近相続したもの、これまでコレクションしてきた仏像などを手放したいと考えているなら、買取業者に相談してみましょう。 仏像の状態や、作家によっては高額買取してもらえるかもしれません。 仏像を高額買取してもらうには 仏像を高額買取してもらうにはさまざまな条件があります。 仏像は、作家によりデザインが違うことから、作家が誰であるかが買取価格に最も影響します。 保存状態が良いか 仏像の高額買取には、保存状態の良し悪しが大きく響きます。 汚れや傷、割れている部分があると買取価格が下がってしまうため、これから仏像を売る予定の方は、保管方法に注意が必要です。 有名な作家の作品や、人気の作品でも保存状態によっては査定額が下がります。 仏像は木、象牙、金、石などデリケートな素材で作られているため、直射日光の当たらない場所で高温多湿を避けて保管しましょう。 付属品や鑑定書があるか 仏像はレプリカも多く出回っているため、オリジナル品かどうかを判別するためには 、鑑定書が必要です。 鑑定書は、一般的に既に亡くなっていて、本物かどうか作者本人に確認が取れない作品に対して作ります。 そのため、鑑定書があるものは本物だとすぐに判断でき、査定もスムーズです。 また、共箱と呼ばれる仏像に付属している箱には、作者の印が入っていることが多く、箱があるだけでその仏像が本物であることが証明されます。 共箱は必ず合わせて査定に出しましょう。 作家物であるかどうか 高額買取対象の仏像は、作家物であることが重要です。 作家物というのは、制作者が自身の意図や思いを載せている作品のことをいいます。 そのため、手法やデザインも伝統に乗っ取ったものだけではなく、作家のオリジナルが含まれている作品を指します。 作家物であるためには、作者が誰であるかもポイントになるため、有名な作家が作った作品であることが、仏像の価値を決めるといっても過言ではありません。 仏像は、素材や保管状態によって価格が変わりますが、それ以上にどの仏師の作品かが大切なのです。 仏師を判別する場合も、先述の共箱に情報が記載されているため、共箱の有無がポイントになります。 仏像を手放すとき、どんな方法がある? いざ仏像を手放すとなると、どの業者に頼めばよいのでしょうか。 回収業者や骨董買取業者など、仏像を回収してくれる業者はひとつではありません。 大切に受け継がれてきた仏像なら、大切に扱ってくれる業者に預けたいものです。 ネットオークションやフリーマーケット 仏像は、ネットオークションやフリーマーケットでも多く取引されています。 海外にも仏像のファンが多く、ネットオークションなら国内にとどまらず海外までより多くの買い手の目に留まるでしょう。 オークションは自分で値段設定ができるため、最低でも希望価格で取引でき、うまくいけば希望価格以上で取引できます。 値引き交渉の対応に追われたり、買い手がつかなかったりすることもあるため、自分で出品するのは労力がかかるのが難点です。 また、仏像への知識があまりなく価値のあるものを誤って低額で売ってしまうことも起こり得ます。 知識がなければ詐欺に合う可能性もあり、自分で出品するのはリスクが高いため注意が必要です。 リサイクルショップで売却 リサイクルショップの魅力は、その場で査定と売却が行われるため、即日売却ができます。 そのため、最短で換金することが可能です。 ただし、リサイクルショップは、仏像などの骨董に詳しい査定士が在籍していることは稀で、仏像の価値にあった査定額にならないことがあります。 売却時に時間の猶予があるなら、まずはオンラインで査定を行っている別の専門業者に査定してもらってから、リサイクルショップに持ち込むのがお勧めです。 不用品回収業者や遺品整理業者へ相談 仏像が複数点ある、他にも回収してほしいものがあるなど、まとめて回収してほしい場合は、不用品回収業者や遺品整理業者へ相談する方法があります。 遺品整理業者は、屋内や倉庫の片付けなども行っている業者が多いため、家を売却予定で家財道具を一掃したい方は活用してみましょう。 不用品回収業者や遺品整理業者は、まとめて回収することを想定しているため、査定額などもある程度業者のルールで決まっており、1点1点の査定額をその価値に合わせて丁寧に変動させない場合があります。 しっかりと価値に合った査定額を求める場合には不向きでしょう。 骨董品買取業者へ相談 骨董品買取業者には、骨董品に詳しい査定士が在籍しているため、安心して骨董品を持ち込めます。 骨董買取業者は買取実績や買取方法が業者によってさまざまです。 しっかりと買取実績を確認し、自分に合った買取方法の業者を見つけましょう。 仏像の査定士が在籍しているかどうかも確認しておくと安心です。 無料査定してくれる業者も多いため、査定後価値を知り手元に置いておきたいと思った場合売却する必要がなく、査定料も取られません。 今すぐに売却予定がなくても、所有している仏像の価値を知っておくために、一度査定にトライしてみるのもお勧めです。 高価買取が期待できる仏像作家は? 仏像は1500年ほど前にインドから日本に渡り、さまざまな仏像作家の手によってたくさんの仏像が作られてきました。 中でも骨董として日本で流通が多いのは、明治から昭和にかけて活躍した仏師の作品です。 高村光雲 高村光雲は、明治19年に東京彫刻会を設立した、日本近代彫刻の父とも言える仏像作家です。 明治維新後の廃仏毀釈運動により、仏師の仕事がなくなり、木彫りも衰退していく中、 高村は、西洋美術を学び、写実主義を木彫りに取り入れます。 この高村の活躍により、日本の木彫りは近代にも残されました。 高村光雲の仏像作品の中では『聖観音菩薩』が人気で、オリジナル品はかなり高額になることが期待できます。 松久宗琳 松久宗琳は『延暦寺東寺五智如来像』、『大阪四天王寺丈六仏』などを製作し、主に京都や奈良で活動した仏像作家です。 京都市内に京都仏像彫刻研究所を設立し、工房で数多くの仏像を製作しました。 寺の仏像製作も多く手掛けていましたが、置物サイズの仏像も人気で、松久の作った原形を銀製や銅製に変えたものが骨董として流通しています。 関野聖雲 関野聖雲は、16歳のとき高村光雲に弟子入りしました。 明治39年に入学した東京美術学校の卒業作品『白拍子』は学校による買い上げとなるほどの実力です。 同校で23年ほど教授として指導していました。 1作品に対し1道具を作ったというほど、道具へのこだわりが強い作家でもあります。 関野の作品は京都浄瑠璃寺の『吉祥天立像』の模刻が有名です。 高村の弟子ともあって、関野の作品も高額買取査定対象です。 松本明慶 現代を代表する仏師松本明慶は、2002年に高野山金剛峰寺に恵果阿闍梨尊像を奉納するなど多くの仏像製作を行っています。 松本は、1991年に総本山より大仏師の称号を授けられ、自身の父と息子の親子3代に渡って皆大仏師の照合を得ているのです。 数々の賞も受賞し、メディアにも取り上げられ、現代仏師としてまたたくまに有名になりました。 松本の仏像は骨董やアンティークとしてではなく、現代アートとしてコレクターに人気です。 100人に1人の逸材といわれる松本の美しい彫刻は、非常に価値のある現代美術作品なのです。 仏像の買取は実績のある骨董買取業者へ相談を 仏像は、共箱に作者の印があることが多く、素人でもある程度見分けられますが、プロにしっかり査定してもらうことをお勧めします。 仏像は仏を彫った作品のため、なるべく丁寧に、そして仏像の価値がわかる業者に買い取ってもらう方が気持ちもすっきりするでしょう。 仏像を手放したくなったら、仏像の査定ができる骨董買取業者へ相談してみてください。
2024.11.30
- すべての記事
- 骨董品買取
- 仏像
-

西洋骨董を高額買取してもらおう
西洋骨董は、家庭内で美術工芸品を楽しめることから、歴史や美術が好きな人々から長く愛されてきています。 アンティークとも呼ばれる西洋骨董は、主に100年以上前の製品を指し、その100年の間に時代の変化により、芸術の流行も変わりました。 そのような芸術の変化を楽しみ、歴史を感じられるところに西洋骨董の魅力があります。 西洋骨董の買取依頼を検討中ですか? 西洋骨董は、現代のモダンなインテリアとマッチしにくく、アンティークな家具やインテリアと合わせなくてはなりません。 価値があるのは知っていますが、インテリアと合わないため、買取依頼をしたいという方も多いのではないでしょうか。 いつの時代も西洋骨董は人気 西洋骨董は、いつの時代にもコレクターが必ずいて需要の高い品です。 100年以上前に作られたもののため、壊れずに残っているものが少なかったり、そもそも流通している数が少なかったりと希少価値があります。 その希少価値の高さが西洋骨董の魅力なのです。 自宅に眠る西洋骨董はありませんか 西洋骨董は、オリジナル品の数が極端に減った場合に作られる複製品や、オリジナル品の一部を変えた変造品などが多く出回っています。 そのため、家に西洋骨董が置いてあっても本物か判断がつかず捨ててしまったり、人に譲ってしまったりすることもあるでしょう。 しかし、その自宅にある西洋骨董は、非常に価値の高いものかもしれません。 西洋骨董を高額買取してもらうには 西洋骨董を高額買取してもらうには、いくつかポイントがあります。 西洋骨董は、かなり古いものなため、査定するには作品に関する情報があればあるほどその価値を判断しやすくなります。 買取を依頼する際は、作品の査定に必要なものをそろえて高額買取してもらいましょう。 付属品はなるべくそろえる 西洋骨董の付属品は、額や箱、保証書などを指します。 これらの付属品があることで、西洋骨董がオリジナルのものだと証明したり、いつ制作されたのか、誰が所有していたのかなどが判別できたりします。 そのため、西洋骨董を集めている人はこれらの付属品がついているものを好んで選ぶ傾向があるのです。 今後新しく西洋骨董を購入する場合や、誰かから譲り受ける場合も、なるべく付属品を合わせて入手しておくと良いでしょう。 作家のサインが入っているか 西洋骨董には、作者のサインや製品情報としてシリアルナンバーが書かれています。 作家のサインは、その作品が本物であることを見分けたり、誰の作品かを判別したりするために重要な手がかりです。 そのため、作家のサインが入っていると高額買取される可能性がぐっと上がります。 作品の中にサインが入っている場合は、作品を持っていくだけで問題ありませんが、箱などの付属品に書かれている場合もあります。 作品内にサインが見当たらなければ付属品に書いていないか確認し、見つからなくても付属品を一緒に持っていきましょう。 シリアルナンバーは、作品の裏や底に書いてあることが多いため、傷をつけないように注意しながら確認してください。 適切に保管しておく 西洋骨董の高額買取には、保管状態も影響します。 しかし、保存状態が良い作品が高額査定されやすいからといって、傷や経年劣化を修復する必要はありません。 素人が修復しようとすると、新たな傷をつけてしまうこともあり、素人の手が加わったことにより査定額が下がることがあります。 汚れをふき取る程度に留めて、現状のまま保管しておきましょう。 また、西洋骨董は100年以上の歴史がある品物のため、これまでの所有者が1人だけとは限りません。 複数の人の手を渡ってきている可能性があるため、前回はどのくらいの金額で購入されているのか、どうやって入手したのかなど作品のこれまでの歴史がわかると査定する際の貴重な資料となります。 このような作品の詳細は保証書に書いてあることが多いため、付属品の保証書や鑑定書は必ず一緒に保管しておきましょう。 西洋骨董を手放すとき、どんな方法がある? 西洋骨董は綺麗に保管しておくのが難しい状況もあるでしょう。 自宅のインテリアに合わないからといって、長期間倉庫などにしまっておくと劣化してくおそれがあり、西洋骨董の価値も下がりかねません。 そこで大切に管理してくれるコレクターに譲りたいという方もいるでしょう。 西洋骨董を手放す方法は個人で売買する方法と、業者に任せる方法があります。 ネットオークションやフリーマーケットで売る ネットオークションには西洋骨董が多く出品されており、ネットオークションで買い取るコレクターも少なくありません。 ネットオークションは、出品者が最低購入額を決められるため、査定額に左右されることもなく、希望価格で取引でき、場合によっては希望価格以上の取引ができることもあります。 フリーマーケットの場合も、売り手が値段を決められるため安心です。 一方で、売り手の希望価格がニーズに合わなければ買い手が現れない場合もあります。 値引き交渉の対応に追われてしまうこともあるでしょう。 また、ネットオークションやフリーマーケットなど、自分で売買契約をする方法では、自身の西洋骨董への知識も豊富でなければなりません。 西洋骨董はプロでも査定が難しく、素人の知識で売買するのはリスクがあります。 買い手の方が知識があり、誤ってオリジナル以外の品物を販売した場合、トラブルになる可能性があるため注意が必要です。 リサイクルショップで売却 リサイクルショップでも西洋骨董を買取しているところはありますが、骨董を査定できる査定士がいる店はあまりありません。 そのため、持ち込んだ西洋骨董の価値に見合った価格がつきづらくなります。 骨董の価値をよくわからないまま査定に出すと、損してしまうこともあります。 査定額の交渉も可能ですが、非常に手間です。 リサイクルショップのメリットは、最短即日で売却できる点でしょう。 すぐにお金に換えたいという人はリサイクルショップに持ち込むのもお勧めです。 不用品回収業者や遺品整理業者へ相談 不用品回収業者や遺品整理業者は、複数のものをまとめて回収してくれるメリットがあります。 そのため、たくさん西洋骨董を所有していたり、他に回収してほしいものがあったりする際は、これらの業者に依頼すると便利です。 遺品整理業者は、室内の片付けを行ってくれるところもあります。 しかし、これらの業者も西洋骨董に詳しい査定士がいないことが多く、自分に西洋骨董の知識がなければ損する可能性もあるため注意しましょう。 まとめて回収してもらえる半面、回収品一つひとつの査定がわかりづらいため、しっかり査定してもらいたい方には向いていません。 骨董品買取業者へ相談 骨董品買取業者にはプロの査定士が在籍していますが、同じ骨董品でも日本や中国などの骨董と西洋骨董は違います。 骨董品買取業者だからといって安心せず、西洋骨董に詳しい査定士が在籍しているかどうかを確認しておくのがお勧めです。 ホームページやSNSなどに記載があることが多いですが、わかりづらければ電話で問い合わせてみましょう。 その際、査定に必要なものも合わせて聞いておくと持ち込む際もスムーズです。 高価買取が期待できる西洋骨董は? 西洋骨董は非常に幅広く絵画や陶器、貴金属や時計、衣類なども含みます。 これらの中でも、高価買取が期待できる西洋骨董はどのようなものがあるのでしょうか。 西洋絵画 西洋絵画は、19世紀後半から20世紀半ばにかけて活躍した作家の作品が多く市場に出回っています。 人気の作家は、ロシア出身の画家マルク・シャガールや、フランス人でパリの日常や風景を描いたモーリス・ユリトロなどです。 特にシャガールは妻に一途だったことで有名で、「愛の画家」と呼ばれており、作品にも愛を描いたものが多いため、ファンがたくさんいます。 彫刻 彫刻は西洋骨董の中でも歴史が古く、有名な作家の作品は高額買取されやすいジャンルです。 日本人彫刻家にも影響を与えたとされるフランスの彫刻家ブルーデルの作品や、同じくフランスの彫刻家であるモロー兄弟の作品は人気があります。 モロー兄弟は、家庭用に作られた小型の彫刻もたくさんあるため、インテリアとして楽しむコレクターも多いのです。 ビスクドール ビスクドールは、19世紀にヨーロッパのブルジョワ階級の中で流行した、陶器でできたフランス人形のことを指します。 代表的な工房はジュモーで、テートジュモー、デポゼジュモーなどさまざまなシリーズの人形が作られました。 数年間しか作られなかったビスクドールなど、希少価値の高いものは高額査定対象です。 オルゴール アンティークオルゴールもファンが多く、海外出張の土産などで日本にたくさん持ち帰られており、西洋骨董市場で人気の品です。 オルゴールは、シリンダー製のものから19世紀末ごろを境に、ディスクオルゴールへと移っていきます。 そのため、シリンダー製のものは歴史が古く、高額買取される可能性が高い傾向です。 また、スイスの「リュージュ」やドイツの「シンフォニオン」など有名ブランドのオルゴールも人気です。 オルゴールはしっかり音が聞こえてこそ価値があるため、保存状態の良さや演奏される曲目も査定額に反映します。 西洋骨董の買取は実績ある買取業者へ相談を 西洋骨董はさまざまなブランドや製品があり、その歴史の長さから査定が非常に難しい分野です。 さらに、非常に高額買取される可能性も秘めているため、安易に買取業者を選ばないようにしましょう。 西洋骨董の買取実績があり、西洋骨董に明るい査定士が在籍していることは必須です。 自宅に西洋骨董がある方は、買取業者を吟味し一度査定してもらってみてください。
2024.11.30
- すべての記事
- 骨董品買取
- 西洋美術・西洋アンティーク
-

世界が注目する刀剣、高く買取してもらうには
日本を象徴するものといっても過言ではない刀剣は、現在、たくさんの人から関心を持たれる芸術品の一つとして変化しています。 刀剣は、刀としての役割のみでなく、見た目の優美さ、厳かな佇まいも、人々の心をつかむものです。 多くの人を魅了する刀剣は、芸術品としての評価も高く、国宝に認定されているものも存在します。 刀剣の買取依頼を検討中ですか? ご自宅にある刀剣を、買取してもらいたいと検討中の方もいます。 しかし、刀剣は刃物であり、扱いにも気をつけなければならず、刀剣の持ち込み先も悩みどころです。 刀剣の買取は、自分で販売したり、業者に買い取ってもらったりする方法があります。 すべての方法に、メリットとデメリットがあるため、ご自分にはどの方法がよいのか考えてから買取を依頼しましょう。 刀剣の価値を理解している業者に依頼する方法は、本来の価値をつけてもらえる可能性が高いでしょう。 いつの時代も刀剣は人気 刀剣は、古くは戦闘時の実用性で、現在はその美しさで、人々の心を奪っています。 刀剣を使用し、戦ってきた多くの人は、その切れ味や使いやすさを求め、長きにわたり試行錯誤してきました。 そして、現在は、その試行錯誤されてきた歴史を、刃の反りや模様などで学んだり、その厳かな雰囲気を感じたりする人が多くいます。 歴史ある刀剣は、理由は違えども長きにわたり、人々を虜にしているのです。 自宅に眠る刀剣はありませんか? 現在、ご自宅の刀剣を手放そうと考えているなら、買取業者への相談をお勧めします。 自分で収集してきた方や、ご家族から引き継いだ方の中には、価値をつけずに手放してしまうのは避けたいと考えている人も多いでしょう。 刀剣は、歴史あるものだと、非常に高い金額がつく場合もあります。 そのため、刀剣に詳しいスタッフがいる業者へ相談すると、刀剣がもとより持つ価値をつけてもらえるでしょう。 刀剣を高額買取してもらうには 刀剣を、高額で買取してもらうためには、見た目のきれいさや作家など、さまざまな条件がそろっていることが重要です。 刀剣は、時代によって、長さや模様などに大きな違いがあります。 また、作家によって評価が大きく変わったり、見た目のきれいさでも評価が変わったりします。 さまざまな条件が重なることによって、価値が上がり、結果、高額での買取につながるため、特に保管の仕方には気をつけておきたいところです。 作家と刀剣のランク 刃の切れやすさと仕上がりのよさによる階級、作家が誰なのかが重要な査定対象の一つです。 刀剣の階級は、それぞれ4つに分けられており、この階級が高ければ高いほど、高額での買取が期待できます。 また、刀剣を作った作家が著名な作家であるほど、高額で買取されるでしょう。 著名な作家の中には、5億円の値段がついた刀剣も存在します。 所有する刀剣が、階級が高いものかつ著名な作家のものであれば、価値が高くつく場合があります。 サイズや種類 刀剣の大きさで価格が変わるため、所有している刀剣のサイズが、どのカテゴリーに当てはまるのか、見ておくとよいでしょう。 刀剣の長さは、主に4つに分けられます。 長いものは80センチ程度、短いものだと30センチ未満であり、長いものから順に、太刀・刀・脇指・短刀と呼ばれています。 特に、太刀は、古くから名刀とされているものもあり、高い価格がつきやすいでしょう。 また、太刀以外の3つでは、刀が最も高値で買取されやすいといえます。 制作された時代 刀剣がいつ作られたものか、この違いで買取額に差が出ます。 最も歴史の長い刀剣は、平安時代よりも前のものであるといわれており、歴史が長ければ長いほど、価格が上がりやすいことが特徴です。 時代ごとに刀剣を使用する背景が違い、その背景の違いにより、刀剣の模様の有無や、強度などに影響が出ているのです。 現代に作られた刀剣を現代刀と呼びますが、現代刀は、ほかの時代の刀剣よりも価格が下がりやすい一方、有名作家のものであれば、高額買取される場合もあります。 刀装具や拵 刀装具や拵は、所有していた武士の個性が出ているため、高額で買取されやすいでしょう。 拵は、安土桃山時代以降に重要視され始め、美しさだけでなく、所有している武士の階級なども判別できる作りに変化していきました。 そのため、有名武士の拵であるほど、その作りこみ方に大きな違いがあるため、高額で買取されやすいのです。 また、有名武士のものでなくとも、拵の美しさが高額買取につながる場合もあります。 保存状態 保存状態の良し悪しで刀剣の買取額が大きく変わるため、保管や手入れには細心の注意を払いましょう。 刀剣は、きれいな状態のものは、高値がつけられます。 きれいな状態とは、刃に傷やサビがなく、作られた当時のままを保っている状態のことを指します。 そのため、傷やサビがついていると、価値が下がってしまいやすいのです。 現在、刀剣を所有している方は、刃に傷やサビをつけないために、保管場所や手入れに十分注意してください。 刀剣を手放すとき、どんな方法がある? 刀剣を手放す方法は、自分で販売する方法か、買取業者に依頼する方法の2種類があります。 ネットオークションやフリーマーケットで販売すると、自分で価格設定でき、希望価格で売れるよさがあります。 その反面、商品が届かないなどのアクシデントに巻き込まれやすい点が、デメリットです。 リサイクルショップで買取依頼すると、当日に自分で買取金を受け取れますが、刀剣の買取を実施していない店舗もあるため、確実に買取されるか分からない場合があります。 不用品買取業者や遺品整理業者に買取を依頼する場合は、自宅にあるほかの遺品なども一緒に買い取ったり、処分したりしてもらえることで、依頼する側の負担が減ります。 しかし、刀剣の専門家がいないことや、すべてまとめての買取額を出されるため、1つの価値が分からないことがデメリットです。 骨董品買取業者には、刀剣の専門家が在籍している場合が多く、しっかりと査定してもらえますが、訪問での買取や、店舗での買取など、業者によって、査定方法が違うことに戸惑う場合があります。 しかし、刀剣は、専門家でなければ価値が分からない代物のため、専門家が在籍する業者に依頼できるメリットは大きいといえるでしょう。 高価買取が期待できる有名な刀剣作家は? 刀剣は、その美しさや歴史の長さ以外にも、作家が誰であるかが価値をつけるうえで欠かせません。 高額での買取が期待できる作家からは、その作りのよさや美しさから、多くの名刀が生み出されています。 また、作家によっては、賞の受賞や、人間国宝に選ばれた人物まで存在しており、刀剣の作家がいかに重要であるかを物語っています。 各時代に、さまざまな有名作家が存在し、現在まで、刀剣のコレクターに愛されているのです。 相州政宗 相州伝の祖と呼ばれる正宗は、鎌倉時代の有名作家の1人です。 1264年に誕生した正宗は、17歳で弟子入りし、その後、さまざまな土地の技術を習得して、相州伝を作り上げました。 正宗は、江戸時代に編集された書物『享保名物帳』に、「天下三作」の1人として取り上げられました。 正宗の刀剣は、織田信長などの有名武士たちが、こぞって愛したことでも有名です。 また、正宗の技術は、正宗十哲といわれる弟子たちに受け継がれ、現代まで、その技術が続いています。 月山貞一 1836年、現在の滋賀県に誕生した月山貞一は、大阪の月山貞吉の下で、11歳から修行を始めます。 その後、「月山貞吉造之嫡子貞一十六歳ニ而彫之、嘉永四年八月吉日」と記した脇差を、16歳で作り上げました。 月山の刀剣は、綾杉肌と呼ばれる、波状の模様に特徴があります。 1876年に廃刀令が出されましたが、以降も刀剣を作り続け、明治天皇などに軍刀を作ったことでも有名です。 1906年には、日本美術保全のための名誉職である、帝室技芸員に任命されました。 高橋貞次 1902年に誕生した高橋貞次は、1917年に、月山貞一親子の元で修業を開始しました。 1936年には、自身の鍛錬場を開き、1938年には、内閣総理大臣賞を受賞しましたが、終戦後、鍛刀禁止令が施行されると、生活苦に陥り、一時は命を断つ決断もします。 しかし、命を断つことで刀作りの歴史が終わると考え、その後も、刀を作り続けました。 その甲斐あり、1951年に、伊勢神宮へ宝刀を作刀し、1955年には、人間国宝に選ばれるなど、刀匠界おいて欠かせない人物となりました。 隅谷正峯 1921年に誕生した隅谷正峯は、1939年に立命館大学入学後、同校の桜井正幸が講師であった、立命館日本刀鍛錬所に所属し、桜井に弟子入りしました。 その後、日本刀鍛錬所傘笠亭を開き、作刀に投じ、以降作刀技術発表会では、計9回の賞を受賞しています。 1981年には、その技術と偉業が認められ、人間国宝に選ばれました。 隅谷は、独自の丁子刃文を開発し、その刃文はのちに、隅谷丁子と呼ばれるほど、刀剣界に名を広めたのです。 刀剣の買取は実績ある買取業者へ相談を 日本の伝統的な文化である刀剣ですが、刀剣本来の価値をつけてから手放したいと考える方が多くいます。 しかし、刀剣の価値を理解している業者は数少なく、吟味せずに買取を依頼すると、価値を低くつけられる可能性があります。 そのため、刀剣の買取を依頼する際は、刀剣に詳しいスタッフが在籍しているのか、刀剣の買取実績は豊富なのか、などを重視して業者を選ぶとよいでしょう。 後悔しないために、業者選びは慎重に行ってください。
2024.11.30
- すべての記事
- 骨董品
- 骨董品買取
- 刀剣
-

蒔絵や漆器は買取してもらえる?高額売却できる条件とは
蒔絵とは、日本の伝統的な漆工芸品の加飾技法の一つです。 漆に金粉を蒔いて描かれた絵や文様は、漆器をさらに魅力的に見せてくれます。 美術的・歴史的価値を持つ蒔絵・漆器は世界中で愛好されています。 骨董品の本来の価値を判断するには、専門知識が必要です。 蒔絵・漆器の処分を検討している方は、実績ある買取業者へ相談しましょう。 蒔絵・漆器の買取依頼を検討中ですか? 蒔絵・漆器を贈り物としてもらったが趣味が合わない、相続などで譲り受けたが使う機会がない、といったことはありませんか。 手放したい蒔絵・漆器がある方は、買取してもらうのがお勧めです。 蒔絵・漆器の作家や制作時期、保存状態によっては思わぬ価値がつくこともあります。 専門知識を持つ業者に査定してもらいましょう。 いつの時代も蒔絵・漆器は人気 蒔絵は奈良時代、漆器は縄文時代から存在したといわれています。 長い歴史の中でさまざまな技法が生まれ、現在でも職人によって制作が続けられている蒔絵の中には、国宝に認定されるような傑作も少なくありません。 はるか昔から人々を魅了してきた蒔絵・漆器は、現代では日本国内だけではなく、海外でも人気です。 特に有名作家が手掛けた作品や古い時代に制作されたものなどは、希少性が高いため、高額で取引されることもあります。 自宅に眠る蒔絵・漆器はありませんか 贈り物やコレクション、相続などで自宅にある蒔絵・漆器を手放そうと考えているなら、買取業者へ相談してみませんか。 買取してもらうことで臨時収入が得られるだけでなく、国内外のコレクターや美術館といった蒔絵・漆器を必要としている方に受け継いでもらえるかもしれません。 なお、蒔絵・漆器の買取を依頼するのであれば、骨董品に関する専門知識を持つ業者に依頼するのがお勧めです。 価値を正しく判断し、適切な価格で買取してもらえるでしょう。 蒔絵・漆器を高額買取してもらうには 高額買取されやすい蒔絵・漆器には共通点があります。 手元の蒔絵・漆器が高く売れそうかどうか知りたい方は、作家や作られた時代などをチェックしましょう。 また、あらかじめ査定でチェックされるポイントを押さえておくことで、買取価格がアップする可能性もあります。 傷や汚れなどのダメージがないか 傷や汚れなどのダメージの有無は、蒔絵・漆器の査定で必ずチェックされるポイントです。 状態のよいものは、買取価格が高くなる傾向にあります。 一方で、目立つ傷や絵付けの剥がれなどがあると評価が低くなりやすいでしょう。 蒔絵・漆器は衝撃を与えないよう丁寧に扱い、湿度にも注意して保管することが大切です。 また、保管中にダメージを受けることもあるため、早めに買取してもらうとよいでしょう。 付属品がそろっているか 箱や鑑定書などの付属品がそろっている蒔絵・漆器は、買い手が見つかりやすくなることから、高額買取してもらえる傾向にあります。 特に蒔絵・漆器の場合、箱の有無は買取価格に影響することが多いでしょう。 作られた年代が古くて付属品がそろっていない場合でも、一部だけでも持っていくと評価がアップする可能性があります。 手元にある付属品は、まとめて査定してもらいましょう。 作家や時代はいつか 作家や蒔絵・漆器が制作された時代も、買取価格を左右するポイントです。 中村宗哲、原羊遊斎などの有名作家が制作したいわゆる作家ものや、明治時代以前に作られた蒔絵は、高額買取が期待できるでしょう。 漆器では、氷見晃堂、飛来一閑などが有名作家の例です。 落款や鑑定書で作家名や制作時期が分かるときはもちろん、作品の詳細が分からないときも査定してもらうのがお勧めです。 専門家に見てもらうことで高額買取につながるかもしれません。 蒔絵・漆器を手放すとき、どんな方法がある? 蒔絵・漆器を手放すのであれば、買取がお勧めです。 ネットオークションやリサイクルショップ、買取業者など蒔絵・漆器を売る方法はさまざまあるため、使いやすい方法を選ぶとよいでしょう。 ただし、方法によって買取価格が異なる場合があることに注意が必要です。 蒔絵・漆器をできる限り高い価格で売りたい方は、専門知識を持つ業者に依頼しましょう。 ネットオークションやフリーマーケットで売却 普段からネットオークションやフリーマーケットを利用している方の中には、蒔絵・漆器も同じ方法で売ろうと考える方がいるでしょう。 ネットオークションやフリーマーケットには、販売希望価格を自分で設定できるというメリットがあります。 蒔絵・漆器の価値を把握している方にお勧めの方法といえるでしょう。 一方、ユーザー同士が直接やり取りするため、トラブルに巻き込まれる可能性があることがデメリットです。 また、買い手が見つかるまで時間がかかる場合もあるため、売却を急いでいるときには注意が必要です。 リサイクルショップで売却 リサイクルショップでも蒔絵・漆器を買取してもらえることがあります。 店鋪数が多いため、自宅の近くにある方も多いでしょう。 もよりの店舗へ蒔絵・漆器を持ち込めば、最短でその場で査定・買取してもらえる可能性があることがリサイクルショップを利用するメリットです。 ただし、リサイクルショップは蒔絵・漆器の買取を専門としている業者ではないため、価値に見合った価格がつかないこともあります。 本来の価値に気づかずに相場以下の価格で手放してしまうおそれがあることがデメリットといえるでしょう。 不用品回収業者や遺品整理業者へ相談 大量の不良品があるときは、不用品回収業者や遺品整理業者を利用する方もいるでしょう。 その際、蒔絵・漆器の買取ができるか相談するのも方法の1つです。 不用品回収業者や遺品整理業者に依頼するメリットは、さまざまなものをまとめて手放せることや、片付けもしてもらえることです。 しかし、「まとめて買取」してもらうことには、1点1点の価値が分かりづらいというデメリットもあります。 また、蒔絵・漆器の専門家ではないため、相場に見合わない価格で買取される可能性もあることに注意しましょう。 骨董品買取業者へ相談 骨董品買取業者は蒔絵・漆器の専門業者です。 知識を持った専門家が査定するため、本来の価値を正しく判断してくれることがメリットです。 無料査定してくれる業者も多いため、気軽に相談してみましょう。 一方、骨董品買取業者のデメリットとしては、蒔絵・漆器の実績が少ない業者もいることです。 安心して買取してもらうには、豊富な買取実績を持つ業者に依頼するのがお勧めです。 また、訪問、店舗、宅配など業者によって買取方法が異なります。 自身が依頼しやすい方法で対応してくれる業者を選ぶとよいでしょう。 買取してもらえる蒔絵・漆器の主な種類は? 蒔絵・漆器にはさまざまな種類があり、それぞれ中古市場における評価が異なります。 査定してもらう前に手元にある蒔絵・漆器の種類を把握しておきましょう。 平蒔絵 一般的に蒔絵といえば平蒔絵を指します。 平蒔絵の制作では、まず漆で絵や文様を描いたところに金粉を蒔きます。 金粉が漆に付着することで絵や文様が浮かび上がるため、乾いたらさらに上から透明の漆を塗って硬化させる工程が必要です。 その後、硬化した漆を研いだり磨いたりしたら完成です。 平蒔絵では、絵や文様の細部まで丁寧に描く繊細な技術が要求されます。 基本的な技術とされていますが、有名作品の多くは平蒔絵の技法で制作されています。 研出蒔絵 研出蒔絵は、蒔絵の中でも古い歴史を持つ技法です。 基本的な制作方法は平蒔絵と同じですが、研出蒔絵では金粉を付着させた図柄に漆を塗って乾燥させた後、硬化した漆を研ぐことに違いがあります。 蒔絵と地の高さが均一になるため、通常の使い方をする限り金粉が剥がれにくいことが特徴です。 また、落ち着いた輝きを持ち、優しい印象を与えるという魅力もあります。 高蒔絵 高蒔絵とは名前の通り、蒔絵が地から盛り上がっている立体的な蒔絵のことです。 高蒔絵は立体的に作られた形の上に平蒔絵や研出蒔絵を用いることで制作されます。 蒔絵を高くする方法はいくつかあり、漆を厚く塗る方法や他の素材を蒔いて形を作る方法などがあります。 絵や文様の美しさだけでなく、工芸品としても楽しめるのが高蒔絵の特徴です。 肉合研出蒔絵 肉合研出蒔絵とは、高蒔絵と研出蒔絵の技法を組み合わせて作られる蒔絵のことです。 工程が多く高い技術が必要であるものの、優美で華やかな表現が可能な技法です。 肉合研出蒔絵では、1つの図柄の中で立体的に見せたい部分に高蒔絵の技法、背景など奥行きを表現したい部分に研出蒔絵の技法を用います。 それぞれの蒔絵の図柄ができたら透明の漆を同時に塗り、高低差が出ないように表面が滑らかになるまで研いで完成です。 漆の中に図柄を閉じ込めたような仕上がりが、肉合研出蒔絵の魅力といえるでしょう。 蒔絵・漆器の買取は実績ある買取業者へ相談を 日本の伝統工芸の1つである蒔絵・漆器は国内外で人気があります。 贈り物や相続でもらったものやコレクションしていたもののうち、不要になった蒔絵・漆器は買取してもらいましょう。 業者を選ぶ際には、買取実績が参考になります。 蒔絵・漆器を適切な価格で買取してもらうには、正しい知識を持つ専門家に査定してもらうことが欠かせません。 価値ある品物を手放す際は、実績豊富な買取業者へ相談しましょう。
2024.11.30
- すべての記事
- 骨董品買取
- 工芸品
- 骨董品全般